2011年3月11日の東日本大震災の発生以降も日本では地震が相次ぎ、さらには気候変動に起因した大規模な水害が頻発するなど、私たちは様々な災害のリスクにさらされています。このような中、2025年1月には南海トラフ地震の30年以内発生率が80%程度に引き上げられました。今後発生が予測される不測の事態にどう向き合えばよいのでしょうか。今回は、心理学や人間工学の視点から災害リスクの軽減に取り組む、近畿大学生物理工学部の島崎敢准教授にお話を伺いました。

不幸な出来事をなくしたいという、一貫した思い
災害リスク軽減の研究に取り組まれたのはどのような理由からでしょうか。
島崎 准教授:両親が子ども時代に戦争で大変な思いを経験した世代ということもあり、私は小さい頃から戦争という人類にとって不幸な行為をなくしたいと考えてきました。大学では国際紛争の解決策を学ぶため国際関係学部に入学します。そこで実験心理学と出会い、その面白さに夢中になりました。また当時は超就職氷河期だったため、とりあえず自分が食べていくため在学中に大型自動車免許や建設重機などの免許を多数取得しました。その後、運転が好きだったこともあり、卒業後はタンクローリーの運転手になりました。日々車を運転していると交通事故が身近になり、よく考えてみると実は戦争の犠牲者より交通事故の犠牲者のほうがずっと多いことに気づいたのです。そこで、交通事故という不幸な出来事を減らしたいという思いが募り、社会に出てから3年目に一念発起して交通心理学を学ぼうと大学院へ入学しました。そして産業安全、医療安全などの研究を経て防災科学技術研究所へ入所したことをきっかけに、現在は災害リスク軽減についての研究に取り組んでいます。
具体的にはどのような研究を行っているのでしょうか。
島崎 准教授:防災は総合学問であり、様々な分野の専門家が学際的な研究を行っています。特に日本は建築など、防災の工学的対策は世界でも群を抜いています。そうした中、私は心理学や人間工学の視点から災害のリスク軽減にアプローチしています。今まであまりスポットライトが当たってこなかった領域ですね。簡単に言うと、人間の行動を変えることで安全につなげようという研究です。実証的な防災心理学を応用して、危ない行動をやめてもらう、安全な行動を増やしてもらうことを目的に研究を続けています。
防災行動の最適解に近づく「メタ認知」

それでは、防災に対して私たちはどのような姿勢で向き合えばよいのでしょうか。
島崎 准教授:防災にはすべての人に共通した最適解はありません。住んでいる場所や家族構成などで状況はまったく異なります。だからこそ各個人が冷静に状況を把握し、最善と思える行動を取ることが求められます。心理学で自分の思考や認知活動などを客観的に捉え、調整する能力を「メタ認知」と呼びます。防災や災害リスクに関して、このメタ認知はとても重要で「自分が何を理解していて何を理解していないか」「何ができて何ができないか」を客観的に考えることで、「今なすべきこと」を行動に移すことができます。
これは、ビジネスの世界でも同じですね。周りの状況を把握・分析し、リスクテイクしながらベネフィットの最大化を図るのがビジネスです。ですからメタ認知は防災においても、ビジネスにおいても必要となる汎用的な能力だと思います。
しかし、いざ被災するとパニックに陥って冷静に行動できなくなるのではないでしょうか。
島崎 准教授:いえ、むしろパニックにならないことが問題です。被災しても自分だけは大丈夫だと思い込んだり、周りの人が落ち着いているのを見て安心したりすることがよくあります。これが正常性バイアスです。皆さんにはぜひ率先避難者になってほしいと思います。誰かが逃げるために走り出せば、みんなも後を追って逃げ出します。
また、様々な情報も冷静に受け止めてください。2024年8月に宮崎県日向灘沖で発生した地震に伴い「南海トラフ地震臨時情報」が発表され、特別な防災対応が呼びかけられました。その後、大きな地震は発生しなかったのでSNS等では「空振りだった」「科学的根拠がない」などと批判的な声が多く上がりました。しかし、これは「空振り」ではなく「素振り」と考えるべきです。素振りは本番に備えた練習で、多くの人々が災害への備えの重要性を再認識する機会になったのではないでしょうか。
「楽しむ」「褒める」ことで災害は怖くなくなる!?

昨今、企業では防災マニュアルを整備するなど安全教育を進めています。安全な行動をとるための教育で効果的な方法はありますか。
島崎 准教授:南海トラフ地震は必ず起こりますから、防災マニュアルや安全教育などを充実させることはとても重要です。ただ、「災害=怖い」というイメージから、防災のことは考えたくないという人もたくさんいます。この怖いというイメージを払拭することが大切です。
例えば、私たちは楽しみながら防災意識を高めようという研究に取り組んでいます。先だって学生たちと一緒に家具固定のゲームを開発しました。これは地震発生までの限られた時間内に家具を固定していくゲームで、多くの学生に体験させると、約半数が家に帰って実際に家具固定に取り組んだという結果が出ました。
また、褒めることで防災意識や安全対策を高める研究も進めています。幼稚園や保育園などの通園バスは日本国内で4万4000台ほど走っており、そこでは事故を起こさないための様々な工夫がなされています。そこで、こうした取り組みを取材し、好事例として冊子にまとめました。運行者の皆さんが、当然のことだと思って取り組んでいる安全対策の中には他の園の参考になるものがたくさんあります。そこでこれらを公表し、褒めることで良い取り組みが広がるし、すでにやっている人も、もっと良くしようと前向きになるという仮説を立て、今は検証作業を行っています。
防災ゲームで楽しむことや安全対策を褒めることは、どのような効果が期待できるのでしょうか。
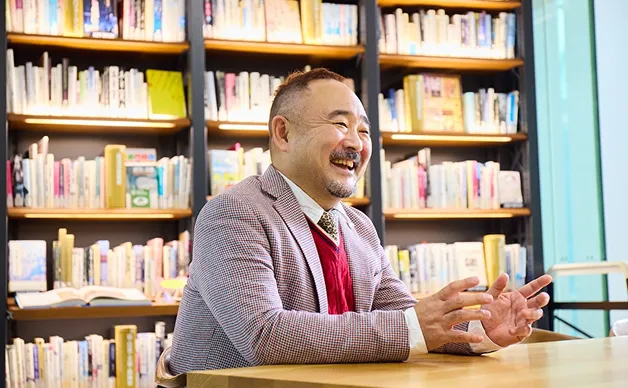
島崎 准教授:人間の行動を変えるには、大きく分類して「叱る」か「褒める」か2つの方法以外ありません。今は叱る方法、つまり規制・禁止するやり方が主流ですが、これにはデメリットがあります。ひとつは、叱られた人はその状況だけを学習するということです。例えば、ある場所で道路交通法の速度超過違反でつかまると、次にその違反者は取り締まられた場所だけに対応すればよいと考えます。もうひとつは、叱ることには正しい情報が含まれていないことです。叱られたその行動はやめますが、次に何をすればよいかが理解できず、行動をやめるという消極的な解決策になります。しかし、褒めることにはどの行動が正解なのかが含まれているので、「もっとやろう」という積極性が生まれます。
「楽しむ」「褒める」は今まであまりないアプローチですが、自発的な行動を促すという点で災害リスクの軽減に有効だと考えています。もちろん、こうした視点に立った取り組みは、企業の防災教育や安全意識の醸成、あるいは家庭内での防災意識の向上にも役立つはずです。災害は怖いですが、防災はリスクを下げる取り組みなのでちっとも怖くありません。メタ認知を意識しながら、みんなで楽しみながら防災に取り組んでください。
Newsletterえふ・マガ登録
NTTファシリティーズがお届けするメールマガジン『えふ・マガ』。
環境や建築、レジリエンスなどに関する社会動向を、有識者のインタビューやビジネスコラム、プロジェクト事例を通じて、日常やビジネスの現場で参考になる情報をお届けします。
お気軽にご登録ください。


