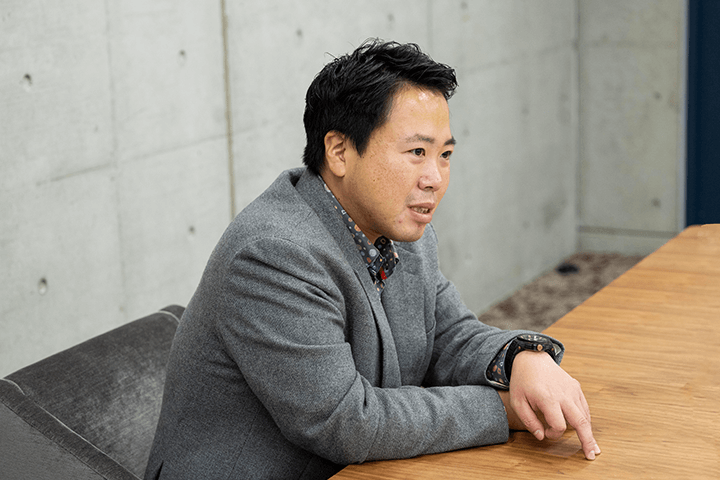センサーなどで空間内の人や物のデータを取得し、そのデータを活用してロボットなどが人をサポートする「空間知能化」という概念があります。今後オフィスが空間知能化された場合、そこで働くワーカーにとってどのような効果が期待できるのでしょうか。空間知能化の可能性や実用化に向けた課題について、中央大学理工学部教授の橋本秀紀さんにお話を伺いました。

ロボティクスとセンシングを応用した「空間知能化」の研究
私は中央大学理工学部電気電子情報通信工学科で、空間知能化に必要とされる要素技術の研究を行っています。空間知能化とは、空間内に存在する人や物の位置、または状態をセンサーなどで取得し、そのデータをもとにAIやロボットなどによって人をサポートする仕組みのことです。
この研究を始める前の修士時代は、制御工学やロボット工学を専攻していました。当時、電気工学分野では産業基盤に直結するパワーエレクトロニクスが注目されており、制御工学はやや不人気だった記憶があります。また、ロボット工学も現在ほど注目されていませんでした。
しかし時代が流れ、ロボット工学が情報工学と結びつき、その可能性が大きく開けました。加えて、現在のAI技術にも生かされているニューラルネットワーク*¹に新たなアルゴリズムが登場したことで、ニューラルネットワーク技術を制御工学に持ち込む発想が生まれました。
制御・ロボティクスの研究を進める中、当時の米国ではインターネット接続を前提にした「Intelligent Space」というキーワードが出てきており、センサーネットワーク関連の研究が増え始めていました。私もインターネット接続を前提として、センサーを多数配置することを中心に研究を進め、技術の応用先を部屋から空間そのものに広げていきます。そして英語ではIntelligent Space、日本語では「空間知能化」としてコンセプトを明確にしていきました。
空間知能化に関しては、当時からさまざまな要素技術が研究されています。例えば、空間知能化に必要なセンシング技術では、カメラなどを用いて空間内における人の動きをリアルタイムで抽出する研究や、天井に超音波センサーを埋め込み、中にいる人の位置情報を取得する研究などが挙げられます。こうした研究は当時から無数に進められていました。
こうした空間知能化につながる技術が生かされた事例もすでに生まれています。1991年6月に噴火した雲仙普賢岳では、その後の土石流対策として除石工事が急がれていました。しかし作業員の安全確保が困難だったため、無人での作業方法が検討されていたのです。ここで実施されたのが、無線技術を活用した作業機械の遠隔操作です。タイプの違う2種類の無線を使用し、現地の画像情報を得ながら、それを見た作業員が手元のコントローラーによって現地の重機を操作して作業を行いました。
この事例で特徴的だったのが、遠隔操作に「人の感覚」を生かしたことです。本来、力の感覚を遠隔で機械に伝えるのはとても難しいことなのですが、現場の作業員は映像を見ながら重機をうまく操作していました。この事例から「空間知能化では人の賢さを活用した仕組みが有効なのでは?」と思ったことを覚えています。
*1 ニューラルネットワーク:人の脳を構成する神経回路網をコンピューター上でシミュレートして再現したような、機械学習プログラムのこと。多層構造のニューラルネットワークは、ビッグデータを利用したディープラーニングなどで活用されている。
空間知能化を実現するさまざまな要素技術
現在私の研究室で手がけているのは「ロボティクス」「センシング」「アクチュエータ」の研究です。ロボティクス分野では、計測技術や制御技術を元にした、人間と協調動作するロボットを、センシング分野では、Wi-Fiや筋電位センサー、カメラなどを用いた非接触生体信号の取得技術や信号処理技術に関する研究・開発をしています。これらを支えるのが、モーターに代表される“動きを生み出す装置”であるアクチュエータです。その高度化も欠かせないため、並行して研究・開発を進めており、これらの技術を組み合わせることで、空間知能化の実用化をめざしています。
このうち「オフィスの空間知能化」に関連する研究としては「Wi-Fiのチャネル状態情報を用いたバイタルセンシング」が挙げられます。これは、市販のWi-Fiデバイスを用いて、空間内にいる人の生体情報を非接触で取得する技術です。Wi-Fiは一般的にはデータ通信に活用されていますが、受信信号の変位を表すチャネル状態情報を解析することで、さまざまな生体情報の推定を可能にすることが知られています。具体的には、呼吸数や心拍数、体動、血圧、位置情報などが推定可能で、例えば、オフィスで働くワーカーの身体情報をこの技術によって取得すれば、働く環境の分析や環境の調整などが可能になるでしょう。また、ワーカーの身体情報を推定する別の方法として、カメラを用いて心拍数・血圧を推定する研究も進めています。
それから、人の顔に筋電位センサーをつけることで、声を発さずに発話内容を認識できる無声発話認識システム「サイレントスピーチ」も、様々な用途に活用できる可能性があります。現在は音声認識システムが高度に発達していますが、その前提は「声を発すること」です。しかし、声を出せなかったり届かなかったりする環境があることも事実です。そこで、声を使わなくても意思疎通のとれる状態を生み出せたら、人のコミュニケーションの幅はさらに広がるのはないでしょうか。このような研究は従来から存在していますが、歩行した状態での発話内容を認識するのが難しいという技術的な課題がありました。しかし私たちは、歩行時の体動を除去する手法を構築し、歩きながら使用できる技術の研究を進めています。
ロボティクス領域では、倒立二輪ビークルを用いた研究も行っています。これは人間の生活圏に適した形状の階段昇降ロボットなどを想定したもので、主に物流領域での活用が考えられます。しかし使い方次第では、災害時の救助や避難活動など、オフィス内外での使用も検討できるでしょう。
人の位置情報や作業情報、さらに生体情報を取得し、AIを活用すれば、その場の人々にどのようなサービスが必要か予測でき、移動、搬送、支援などを行うロボットを迅速に配置することが可能となります。これにはさまざまな利用シーンが想定され、オフィスの属性やワーカーの属性なども実に多様かつ複雑であるため、従来のITでは取り扱いが難しかったものです。しかし、生成AIの登場によって、これに対応することが可能となり、新たなサービスを生み出すことも現実的になりつつあります。まるで一つの生命体のように、オフィス自体がセンサー・アクチュエータ・ロボットを自由に駆使することで、オフィスへ集う人々の快適性を支援し、さらには知的に刺激し創造性を喚起させるようになっていくことが期待できます。
オフィスの空間知能化によるメリット
もしオフィスが空間知能化できたら、ワーカーや企業にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。代表的なメリットは、オフィスの快適性が向上し、ワーカーの生産性が高まることです。例えば、ワーカーの生体情報を収集し、そのデータに基づいてオフィス内の温度や湿度を適切に調整したり、オフィス空間に流す音楽を変化させたりして、ワーカーの状態や働く環境をさまざまな側面から制御・支援できるようになります。また、センシングで得たその他の情報も活用すれば、オフィス内のコミュニケーションの活性化やエンゲイジメントの向上なども見込めるかもしれません。
さらには、収集した生体情報を元として、ワーカーの健康を管理・維持するようなことも考えられます。例えば「Aさんは数値的に疲労が溜まっているから、休息を促すアラートを出そう」「Bさんは血圧が高めだから、健康面での指導を行おう」といった、それぞれのワーカーに対する個別のアプローチも可能になります。こうした取り組みによってワーカーが快適かつ健康な状態で働けるようになれば、これまで以上のパフォーマンスを発揮することが期待できるのではないでしょうか。
こうしたオフィスの空間知能化を実現するために今必要とされているのが、要素技術を社会やビジネスにインテグレーションするプレイヤーの存在です。例えば私は、自身の研究を突き詰めることには長けているものの、技術を実装するために必要な要件までは検討しかねます。こうした要件を把握しているのは、自社ならではのマーケットや商材を持っている企業だと考えています。近年では産学連携の事例も増えてはいますが、より一層の取り組みが求められます。
最後に、十数年先の「未来のオフィス」に思いを馳せてみましょう。私は将来的に、オフィスが「使えば使うほど価値の上がる空間」になったら面白いのではないかと思います。たいていのものは、使えば使うほど価値が下がっていきます。しかし、骨董品や歴史ある建築物などに一定の価値があるように、オフィスもそこで働くワーカーのさまざまな生体情報や、働く中で生まれた思いのようなものが空間の“記憶”となり、その記憶によって価値が高まるようになるかもしれません。
これが実現できたら、例えば、過去に大きな成果を上げた企業のオフィスが、その後も一定の価値を持つ可能性があります。また、そのオフィスの“記憶”を元に、次に入居した企業が新たな価値を発揮していくような好循環も生まれることでしょう。
そしてこれからの時代、人とロボットの共存、共生はより一層現実味を帯びてきます。特に、近年の生成AIの急速な進化には目をみはるものがあります。生成AIが自身の進化に必要な要素を発案できるようになり、それに必要な工程や作業を人間が担う。これも、ひとつの共存・共生の形となるでしょう。
こうした未来の可能性を見据えながら、まずは現在、そして数年先の「理想のオフィス」について考えを巡らせてみてはいかがでしょうか。
Research Report資料ダウンロード
リサーチレポート集発行!
多方面の有識者からのヒントがここに。
最新データを今すぐダウンロード
Newsletterえふ・マガ登録
NTTファシリティーズがお届けするメールマガジン『えふ・マガ』。
環境や建築、レジリエンスなどに関する社会動向を、有識者のインタビューやビジネスコラム、プロジェクト事例を通じて、日常やビジネスの現場で参考になる情報をお届けします。
お気軽にご登録ください。