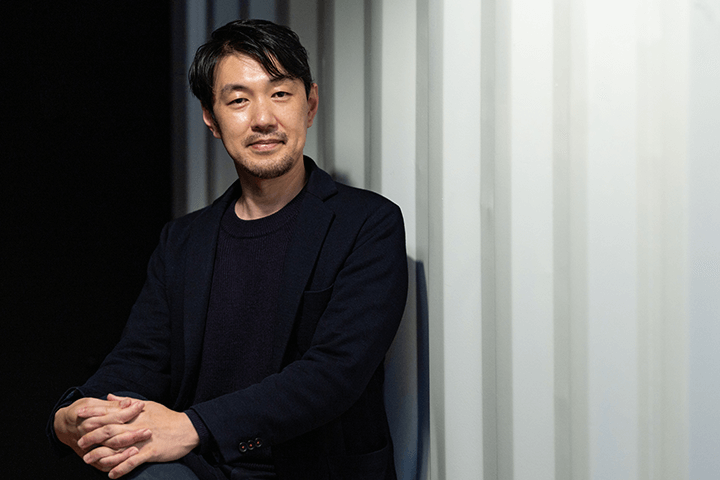近年、人的資本経営の推進に向け、組織の枠組みを超えて新たな学びを得る「越境学習」に注目が集まっています。今、多くの企業が取り組もうとしている背景や実践するうえでの重要なポイントのひとつである「アンラーニング」などについて、グロービス経営大学院准教授、KIBOW社会投資ファンド プリンシパルの松井孝憲さんにお話を伺いました。
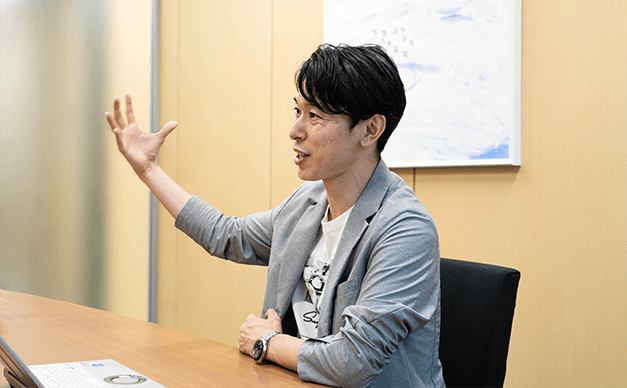
越境学習とは自身の「視野を広げる」学び
私はグロービス経営大学院の准教授や、社会起業家向けのインパクト投資に取り組むKIBOW社会投資ファンドのプリンシパルを務めながら、越境学習の研究活動にも従事しています。
元来、私の関心領域は「ソーシャル×ビジネスの協働」で、学生時代、国際関係論を学んでいた頃に社会起業家という存在を知りました。大学院の修士課程を修了した後、コンサルティングファームへ入社するとともにNPO法人へも参画しました。そしてキャリアを通じて、ソーシャル領域とビジネス領域を橋渡しする活動を今もなお続けています。
越境学習とは、例えば、ソーシャル領域とビジネス領域のような境界を乗り越えて往還することで学びを得る学習です。現在の研究へ取り組む背景には、関心領域である「ソーシャル×ビジネスの協働」への思いがあります。そのためにも、越境学習のより深い理解を促進し、広く普及させることで、双方領域のさらなる活性化を後押ししたいと考えています。
昨今、越境学習に取り組む企業が増えていますが、一般的な学習との違いについてお話します。
一般的な学習とは、ある特定の領域において知識やスキルを段階的に獲得していくプロセスをさします。例えばテストの点数を上げるために、体系化された知識が記されている教科書や参考書を読みながら知識を得ていく、学生時代の試験勉強をイメージすると分かりやすいと思います。
これに対して、越境学習とは、従来慣れ親しんだ領域とは異なる場や知識を体感し、適応するなかで、既存の知識やスキル、常識などを相対化していくプロセスです。言い換えると、越境学習とは知識やスキル、常識などを垂直方向に「伸ばす」のではなく、水平方向に「広げる」ことを目的にした活動と言えます。
では、なぜ越境学習が必要なのでしょうか。個人の観点でいえば、変化し続ける環境に適応しながら自らキャリアを開拓する能力である「キャリア・アダプタビリティ」の向上が挙げられます。人間は長期間、同じ環境や組織のなかで過ごしていると、視野狭窄や成長の頭打ちに陥りやすくなります。その結果として、キャリアへの不安やモチベーションの低下に繋がる可能性があります。そうした際に、越境学習を通じて普段とは異なる環境への適応力を養うことで、キャリア・アダプタビリティが向上し、自身のキャリアを主体的に構築する能力を獲得できるのです。
一方で、企業組織にとっても、越境学習は大きなメリットがあります。その一つが、集団浅慮(グループシンク)の回避です。硬直的で凝集性の強い組織は、多様な観点に基づいた意思決定ができず、非合理的な結論を導き出してしまいます。しかし、越境学習で異なる組織の常識や価値観を学んだメンバーがいれば、硬直的な空気を打破し、集団浅慮の歯止めになってくれるでしょう。
もう一つのメリットとして、越境学習は人的資本経営の推進にも貢献します。人的資本経営においては、人材の能力をいかに引き出し、向上させるかが重要なカギです。しかし、人に秘められたさまざまな特性や可能性、能力を自社の業務や環境だけで開花させられるとは限りません。その点、越境学習では自社とは異なる知識や行動が求められるため、潜在的な能力を顕在化できる可能性があります。
私が以前携わっていた越境学習のプロジェクトに、次世代リーダーを育成する目的で参画している企業がありました。その企業はビジネスモデルが比較的シンプルで、営業手法や商流も確立されているため、業績は安定していました。しかし一方で、従業員が非連続的に成長しにくく、優秀層の社員のモチベーションの停滞や、前例を踏襲する以上の組織成果を目指すことが困難になるという課題がありました。そのため、次世代のリーダー候補である優秀な人材を越境学習に派遣し、普段とは異なる環境への適応や新たな知識の習得を促すことで、次世代リーダーへの成長を後押ししていました。
一般社員から管理職への昇進など、キャリアアップの過程では、求められるスキルや行動がガラッと変わる瞬間が存在します。そうした場面に適応できる人材を養成するためにも、越境学習は有効なのです。
越境学習に欠かせないアンラーニング
アンラーニングとは、未知の環境に適応するために、これまで慣れ親しんだ常識や知識を意図的に捨ててみる学習方法のことで、越境学習を実践するうえで重要なポイントです。越境学習の現場に身を置けば、これまでには体験したことのないシチュエーションや意思決定の場面に必ず直面します。そうした際に、既存の常識や知識に固執していては、環境にうまく適応できません。越境学習をより効果的に実践するためにも、アンラーニングが必要なのです。
アンラーニングでは二つの行動が発生します。一つが、これまで習慣になっていた判断や行動をやめてみること、もう一つが、これまでの習慣や行動を新しいやり方にアップデートすることです。この二つのうち、特に重要なのは後者だと考えています。これまでの習慣や行動が「A」だとすれば「A’」にアップデートするイメージです。既存の知識やスキルが通用しない場面で挫けることなく、これまでの経験などを踏まえて新しく習慣や行動をアップデートしていくことで、新たな問題解決の方法を身に付けられるのです。
社内での越境学習を可能にする「実践コミュニティ」
「越境学習」と聞くと、普段のオフィスや職場から遠く離れた場所に身を置かなければならない、あるいは物理的な移動が必須である、といった誤解がしばしば見られます。
しかし、必ずしも学習のために場所を変えたり移動したりする必要はありません。例えば、大企業において部門を横断して新たな場に身を置いて学びを得ることも越境学習の一つなのです。
その意味では、大企業では社内での越境学習を実現しやすいと言えます。さまざまな人材が交流する場を設け、それぞれの常識や価値観をぶつけ合いながら、相互に学びを得ていくという越境学習を実施することもできるでしょう。
このとき、参考になる概念として「実践コミュニティ」*¹があります。これは、あるテーマについて共通の関心や熱意を共有し、持続的な相互交流を通じて知識を深めていく場を指します。この実践コミュニティを社内に構築できれば、越境学習を推進する場として活用できるでしょう。
ここで重要なのは、実践コミュニティでは「自発性」や「自律性」が重要な成立要件であるということです。例えば、経営層や上司など組織からの「やらされ感」が少しでもあると、実践コミュニティの効果と価値は大幅に低下してしまいます。企業が実践コミュニティを構築する際には、従業員や場の自発性や自律性をいかに担保するのかが、極めて重要なポイントです。
では、実践コミュニティを築くために、企業や経営層はどのようなアプローチを取るべきでしょうか。一つは「認めること」です。従業員の自律的な取り組みを承認し、社内に情報発信するなどして、企業が従業員の新たな学びを推奨していることをアピールします。ある企業が実践している、勤務時間の20%を通常業務と異なる学習や活動に充てることを認める「20%ルール」は、このアプローチの一つです。
そして、もう一つが「支援すること」です。実践コミュニティを運営するためのスペースや予算、その他のリソースを提供することで、その活動を組織的に支えていきます。
例えば、オフィスなどでの「スペース」の提供は分かりやすい支援策の一つです。ただし、誰もが自由に行き来できる、オープンなスペースにすることが大切です。私の経験から言っても、物理的に壁に囲まれたスペースは、心理的な壁も生じて「ブラックボックス化」し、他のコミュニティへの行き来が阻害され、越境が起こりにくくなります。社内で越境学習を推進したいのであれば尚更、オープンなスペースを確保し、さまざまな立場の従業員が行き来できる場を設けるのが望ましいでしょう。
さらに、実践コミュニティでの学習を促すために欠かせないのが「伴走者の存在」です。実践コミュニティでの活動は自発性・自律性をベースとするものの、すべてを従業員の意思に委ねていると機能不全に陥るケースもあります。そのため、適切な距離感で従業員の自律性を保ちつつ、学習を促す伴走者の存在が不可欠です。その際には、従業員の立場や属性によって掛ける言葉を変えてみるといった細やかな配慮が有効でしょう。
*1 実践コミュニティ:文化人類学者のジーン・レイヴと教育理論家のエティエンヌ・ウェンガーが提唱。
自ら体感することで伝わる、越境学習の価値
人材の価値が企業の命運を左右する昨今、越境学習の重要性はより高まっていると感じます。人的資本経営の関連施策に携わる担当者の方々には、まずは自ら越境学習を実践することをお勧めしたいです。そしてその魅力や意義について、経験からアピールしてはいかがでしょうか。
なお、実践する際に着目してほしいのが、越境の現場における「熱量」です。越境学習の定量的な効果を測定する方法は確かにありますし、実践者にインタビューをすれば定性的な効果も可視化できます。しかしそれ以上に、未知の場所に身を置いて、新たな行動や思考を身に付けようとする従業員には独特の熱量が感じられます。その熱量は、他の従業員に伝播し、組織そのものを変革するポテンシャルを秘めていると私は思います。
そのため、企業として越境学習を後押しするのであれば、まずはこの熱量を経営層やマネジメント層に体感してもらうべきだと思います。自社の従業員が越境学習を実施している場に立ち会ってもらい、独特の熱量で未知の環境に挑んでいる様を目の当たりにすれば、越境学習の価値がより伝わります。その結果、取り組みの力強い味方になってくれるのではないでしょうか。ぜひ実践してみてください。
Research Report資料ダウンロード
リサーチレポート集発行!
多方面の有識者からのヒントがここに。
最新データを今すぐダウンロード
Newsletterえふ・マガ登録
NTTファシリティーズがお届けするメールマガジン『えふ・マガ』。
環境や建築、レジリエンスなどに関する社会動向を、有識者のインタビューやビジネスコラム、プロジェクト事例を通じて、日常やビジネスの現場で参考になる情報をお届けします。
お気軽にご登録ください。