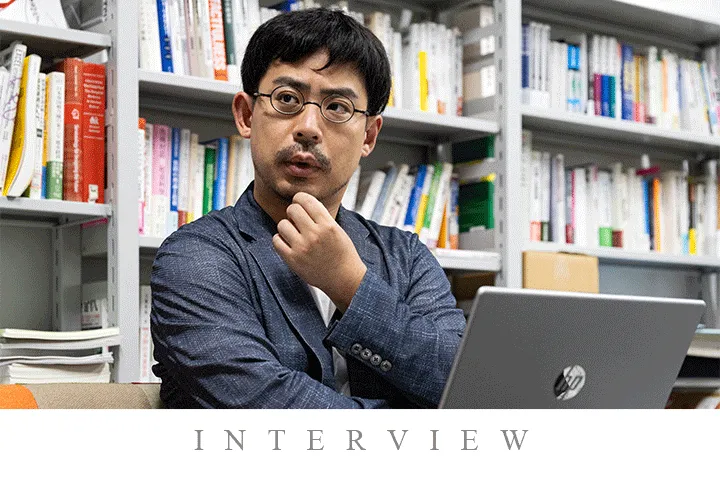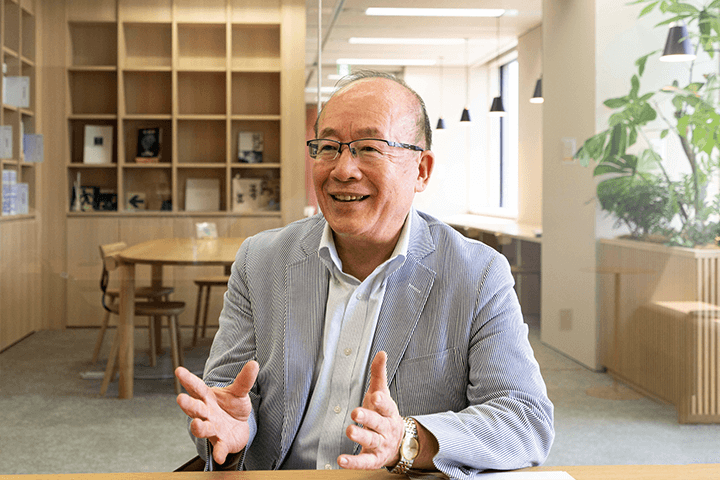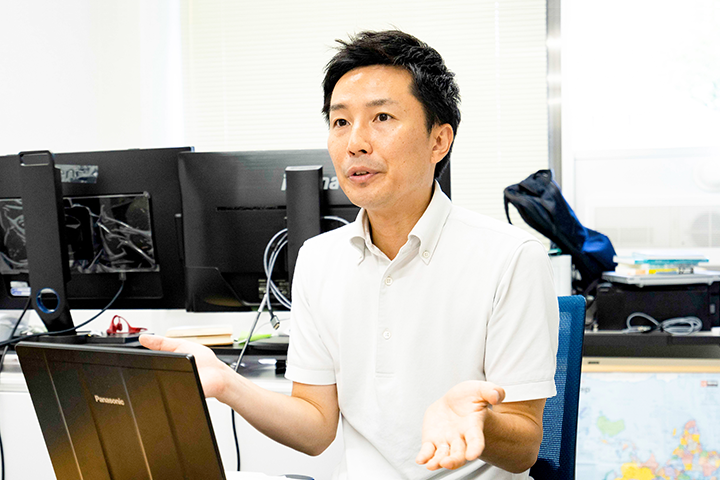1990年代末から2010年代初頭にかけて生まれた「Z世代」が、社会や文化だけでなく、ビジネスシーンにおいても存在感を高めつつあります。企業においてZ世代の活躍を導くためには、どのような試みや取り組みが求められるのでしょうか。東京大学大学院経済学研究科講師の舟津昌平さんにお話を伺いました。

“Z世代のイメージ”に投影される「年長者からの期待」
私は東京大学大学院経済学研究科に所属する経営学者です。専門は経営組織論で、担当する講義の教科書として執筆した『組織変革論』(中央経済社)は、組織変革の事例を数多く扱っており、経営学専攻の学生だけでなく、実務家の方にも読んでいただいたようです。
一方で、学生とのゼミ研究の内容を発展させた『Z世代化する社会』(東洋経済新報社)では、いわゆる「Z世代」を対象にライフスタイルや消費活動、就職活動、キャリア観などについて論じました。
皆さんは、Z世代にどのようなイメージを持っていますか。「デジタルネイティブ」で、あらゆるデジタルツールを使いこなす先端的な人物像でしょうか。あるいは「コスパ・タイパ重視」でムダを嫌う人が多いと捉えているかもしれません。
それらは一面的な事実ではありますが、一方で、いつの時代の若者にも共通した普遍的な特徴が、さもZ世代特有のものとして挙がることもあります。いつの時代も若者は経験に乏しく、いわば「世間を知らない」存在です。そうした人々が年長者から異質な存在に見えるのは当然でしょう。
むしろ私は、近年のZ世代に対する報道などから、年長者が若者に対して「社会や組織の停滞を打破する役割」を期待しすぎている側面が大きく、そうした過剰な期待がZ世代に対するイメージに反映されているのではないかと考えています。
Z世代が今「困惑している」理由
Z世代の一部は「そうした年長者からの過剰な期待やまなざしに戸惑っている」といえます。
新卒採用のシーンで考えてみましょう。私のゼミ生は、ある企業の面接で「挫折体験を教えてください」と質問されたそうです。対して学生は「挫折したことはありません」と答えたとか。すると面接官は呆れたように「ちゃんと準備してきてください」と返答したとのことです。
学生に聞くと、昨今の新卒採用の面接では挫折体験について尋ねられるのが定番化しているそうで、多くの就活生が「挫折エピソード」を用意しているようです。しかし過去の体験は当然人それぞれであって、「準備してきてください」という返答は見当違いと言わざるをえないでしょう。
求める人材像に「創造性豊かな人材」「失敗を恐れずにチャレンジする人材」といった特徴を挙げる企業は少なくありません。それもあって、「挫折エピソード」のような定型的な質問に整然と回答できる就活生を高く評価するようになります。
リアルなZ世代の特徴としてよく挙がるのが「失敗を過剰に恐れる」ことです。その要因の一つが、年長者が若者に期待する能力と、その結果として突き付けている要求が、実像と乖離していることにあると私は考えています。
先の例で言えば、「挫折エピソードは定番の質問なのだから、事前に準備してほしい」という面接官の意図は分かります。また、こうした画一的な対応を取ってしまう根本的な原因に、「人材の評価が極めて難しい」という事情もあります。とはいえ、そうした定型化がZ世代を困惑させているのは確かです。
さらに言えば、Z世代は「自分らしさを見せると評価されない」ということも察知しているため、本音で話すことを避けます。本音を言えば嫌がられるかもしれない。相手におもねって、そして本音を隠した行動が結果的に受け入れられることが、さらに社会や年長者への不信感に繋がり、失敗を過剰に避ける傾向を生んでいると考えられます。
「リスクを取って投資すること」が組織変革の第一歩
Z世代の活躍を期待する背景には、昨今注目されている「人的資本経営」も関係しているといえます。
この人的資本経営に関する議論をはじめとして、日本企業はしばしば「生産性が低い」と指摘されます。この指摘は一般的に「仕事の効率が悪いこと」を想起しがちですが、近年の研究では、日本企業の「投資の少なさ」が、生産性を低下させている主要因だと言われています。つまり、採用、教育、生産設備、賃金、就業環境などへの投資の少なさが、「生産性の低さ」として現れているのです。
では、企業はどう対応すればよいのでしょうか。私は、今以上に「リスクを取って投資すること」が求められていると考えています。
例えば、採用や人材育成のシーンであれば「自社なりの『求める人物像』を定めて、独自の採用選考を行う」「求める人物像を採用するのが難しいことを前提に、入社後の教育や研修に力を入れる」などの行動が挙げられます。このようなリスクを取った行動や施策は、Z世代が感じている「期待と要求の不一致」を是正し、企業への不安や不信を緩和する一助になるでしょう。
また、人的資本経営の実務を担う人事担当者には、IRやファイナンスの知識など、従来よりも広範な業務知識が必要となる傾向にあります。よって、人事担当者のリスキリングに投資することも、企業がとるべき行動の一つではないでしょうか。それは決してコストではなく、会社に利益をもたらすための投資だといえます。
加えて、「リスクを取る」と言っても、無謀な挑戦を奨励しているわけではありません。経営学では、不確実性のある市場環境下で企業が競争優位を得るための要素として、「ダイナミック・ケイパビリティ」の有用性を説いています。ダイナミック・ケイパビリティとは、企業が変化する環境に対応して自身を変える能力のことで、「既存の資源や能力を活用することで、新しい価値が生まれる」という点を特徴としています。
つまり、必ずしも、リスクを取るために目新しい制度を取り入れたり、高額の報酬で他社から役員を引き抜いたりするばかりではなく、既存の資源や人材を組み換えることで新たな価値は十分に生まれ得るのです。既存の資源や人材の組み換えであれば、未知の領域へのチャレンジよりもリスクは低く、多くの企業が取り組みやすいでしょう。
そして、成功事例に捉われすぎないこともポイントだと思います。ビジネスメディアを中心に、企業の成功事例が数多く発信されていますが、それらの事例が長期的に見ても成功 と言えるかは疑問です。ある時点では成功に思えた結果も、後に振り返ってみると取るに足らない出来事だったというケースは少なくありません。何を「成功」とするかは状況依存的であり、成功事例が必ずしも汎用的なお手本になるとは言えないのです。
そこで「チャレンジしている企業」をお手本にするのはどうでしょうか。例えば、ある大手IT企業は、日本で初めて成果主義を取り入れ、ジョブ型の新卒採用を開始するなど、チャレンジングな取り組みで知られています。すべてのチャレンジが成功したわけではないでしょうが、同社は長年に渡って業界トップの地位を維持し続けていますし、何よりチャレンジする組織文化が深く根付いています。その組織文化がさらなるチャレンジを生み、新たな価値を創造しているのです。
この「リスクを取る」ことは、変革への本気度を組織内に発信する絶好の機会でもあります。「この会社は本気で変わろうとしている」というメッセージを届けることで、変革を受容する組織の土壌が培われます。Z世代に対しても同様で、「この会社はチャレンジを歓迎する」という実績や態度を示すことが、若い世代の創造性や自主性を引き出し、挑戦を促すと思います。
Z世代への対応は「プロダクトアウト」のアプローチで
製品開発やマーケティングに「プロダクトアウト」と「マーケットイン」という二つのアプローチがあることはよく知られています。その二つに倣えば、昨今のZ世代に対する企業の対応は、ニーズや特性に配慮して社内制度などを整備するマーケットインのアプローチに偏重しすぎているのではないでしょうか。
もちろんそのアプローチも大切ですが、一方で、自社の価値観や態度を示して若い世代を惹き付けるプロダクトアウト的なアプローチも欠かせません。なぜなら、マーケットイン的なアプローチは、従業員に手厚い福利厚生や就業環境などの「リソースの多寡」に左右される面があるからです。こうした制度や環境面の充実は人的資本投資のひとつではありますが、マーケットイン的なアプローチで自社独自の魅力や働きがいを形作るのは、非常に難しいと言えます。
また、Z世代を過度に優遇したマーケットイン的アプローチの裏側で、他の世代の従業員に皺寄せが及ぶような事態は避けるべきです。不均衡な状況を是正するためにも、企業はプロダクトアウト的な発想で、自社の方針をしっかり示して従業員を牽引していく姿勢が必要だと考えています。企業として何に注力するのか、どんな人材を求めるのかといった方針を社内に示し、浸透させるなどの施策が考えられます。
昔から一貫した「プロダクトアウト」の会社として、国内大手自動車メーカーが挙げられます。そのメーカーは今なお公式ウェブサイトに「フィロソフィ」に関するページを設け、創業者の時代から変わらない価値観があることを明示しています。創業者が生きた時代をふまえると、Z世代に「迎合」しているわけはありませんよね。しかし、結果的にはそうした明示的なメッセージが若者を誘引することも、当然あるはずです。
いずれにせよ大切なのは、「自社らしさ」をいかに確立し、日々の活動のなかで体現していくかということです。目まぐるしく変化する社会環境やトレンドの中で「自社らしさ」を貫くことは、リスクでもあります。しかし、社会や業界の慣習を踏襲することが重要で「自分らしさを見せると評価されない」と怯えている企業は、Z世代と同じ状況に陥っているかもしれません。
リスクを取ることで、企業としてのアイデンティティが形作られ、組織の一体感や変革への意欲が醸成されます。その姿勢や熱量はきっとZ世代の目にも「信頼に値する企業」として映るのではないでしょうか。
Research Report資料ダウンロード
リサーチレポート集発行!
多方面の有識者からのヒントがここに。
最新データを今すぐダウンロード
Newsletterえふ・マガ登録
NTTファシリティーズがお届けするメールマガジン『えふ・マガ』。
環境や建築、レジリエンスなどに関する社会動向を、有識者のインタビューやビジネスコラム、プロジェクト事例を通じて、日常やビジネスの現場で参考になる情報をお届けします。
お気軽にご登録ください。