
ハイブリッドワーク下での課題を解決に導くチェンジマネジメントと、ファシリティマネジメントの価値
2022年11月01日マネジメント
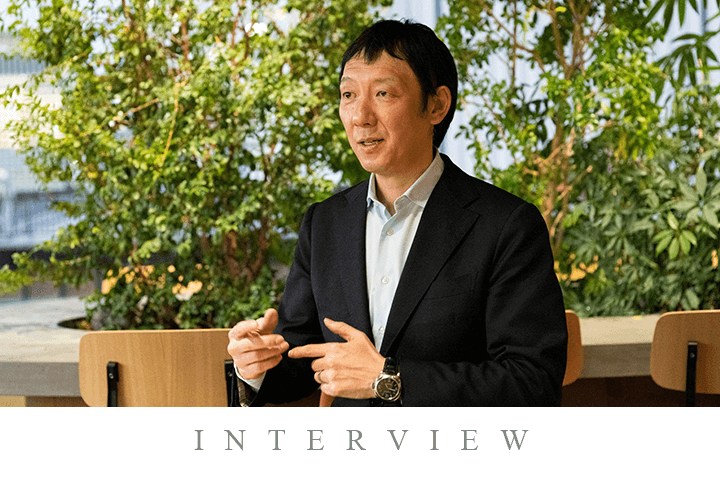
企業が所有または賃借している不動産を戦略的に活用するCREマネジメント。人々の価値観の変化や働き方の多様化が進む今、企業は自社ビルやオフィスをどのように活用すべきなのでしょうか。国内のファシリティマネジメント(以下、FM)の普及定着を図り、ファシリティマネジャーの育成などを推進する公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会(以下、JFMA)でCREマネジメント研究部会長を務める堀雅木さんにお話を伺いました。

私は新卒で入社した第一生命の不動産部に勤務したのち、米ミシガン大学で建築・不動産に関するマネジメントの修士を取得しました。帰国後には所属企業にて、社内でのFMの推進や不動産のサステナビリティに関する取り組みを手がけてきたほか、JFMAの一員として研究活動や情報発信に携わっています。不動産投資、自社用オフィスビルの建築プロジェクトマネジメントや社内FMについての職務経験を活かして、ビルオーナー(貸し手)とビルテナント(借り手)の両者の立場からCREマネジメントについて思考できるのが、自身の強みだと思っています。
自社で保有する不動産の利活用を意識した企業活動、いわゆるCREマネジメントは1970年代に米国で広まり、2000年代以降、日本でも普及してきました。FMを担当するファシリティマネジャーにとって、自社ビルやオフィスの効率的な運用は、今や日常的な業務になったといって良いでしょう。
しかし近年、CREマネジメントには新たな役割が求められていると私は考えています。変化の著しい社会の中で人々の価値観は多様化し、コロナ禍をきっかけに働き方も大きく変化しました。ある人が都心のオフィスで働いているかと思えば、同じ会社の人がリゾート地のビーチでワーケーションしているということもあり得ます。こうした環境下では、従来のオフィスビルにおいて重要視されてきた「都心の駅近くに位置し、豪華なエントランスがある」などの魅力だけでは、従業員の満足度を高めることは困難になってきています。また、ビルオーナーの企業にとっても、こうした従来の魅力だけを訴求し、テナントを募って収益を上げるのは年々難しくなっていると感じます。
初期のCREマネジメントは、企業不動産に関わるコストを最小化することで企業価値を最大化させる「効率化」が主流でした。この概念の下で作られたオフィスビルは、どこか画一的でゆとりのないものになりがちです。しかし、CREマネジメントを「価値創出」を目的に行うことができれば、自社ビルやオフィスに新たな価値を付加し、従業員のエンゲイジメント向上や働きがいの増進、ひいては従来の効率化以上の企業価値の向上を促すことができると考えています。
この「価値創出を目的に行うCREマネジメント」を、私は「攻めのCREマネジメント」と呼んでいます。攻めのCREマネジメントは、「オフィスビルのありかた」の問い直しが求められる現在において、その可能性を最大限に引き出すことができる取り組みなのです。
攻めのCREマネジメントはどのように実践すればよいのでしょうか。取り組みにおいて、重視すべき観点が二つあります。
一つ目はサステナビリティです。近年、オフィスビルの環境負荷軽減など、企業にサステナビリティへの取り組みを求める社会的要請が高まっています。しかし、サステナビリティは必ずしも建物の環境性能向上などに限定されるものではありません。組織やビジネスを持続可能な状態にして、長期的な成長に導くといった取り組みも、サステナビリティの一つといえるでしょう。
例えば、オフィスのコミュニケーションスペースが従業員にうまく利用されなければ、組織内コミュニケーションが不足し、部門間の連携に支障をきたしたり、イノベーションを阻害したりするおそれがあります。これらは組織の持続可能性を損ねる要因にもなるでしょう。そのため、攻めのCREマネジメントを実施する際には、ハードとソフトの両面においてサステナビリティを意識する必要があります。
そして、もう一つがウェルビーイングです。ウェルビーイングも「健康」や「快適」といった狭義に捉えられがちな概念ですが、幸福、安全性、包摂、満足感など、より広い意味として捉えて、CREマネジメントに落とし込むことが重要です。例えば「『健康』が重要なのだから食堂のメニューは健康食のみにする」という施策がウェルビーイングに適っているのかは疑問です。むしろ「健康」を押し付けすぎて、豊かさや満足感をないがしろにしているようにも思えます。
「自社の従業員が心身ともに豊かで健やかになり、いきいきと過ごせる空間やサービスはどのようなものなのか?」という深い考察や洞察に基づいた環境づくりが、新たな価値をオフィスに付与してくれるでしょう。
事例として、当社が所有する東京の日比谷に所在するオフィスビルを紹介します。同ビルは1938年竣工、1993年に増築リノベーションをおこなった歴史ある建築物で、当社以外に複数のテナント企業も入居しています。2022年にはニューノーマル時代における働き方への対応やテナントビル機能の強化を目的に、全館のリノベーションを実施。サステナビリティとウェルビーイングの視点を取り込んだオフィスビルとして新たに船出しました(第一生命日比谷ファースト)。
特に象徴的なのが、ビルの共有部分でもあり、食堂やコンビニなどが配置されているウェルビーイングフロア「LOFFT」です。300坪以上の空間を一つの公園として捉え、緑豊かな空間で会話、休憩、食事、仕事を思い思いに楽しめる場として構成されています。このフロアの特徴は、テナント企業はもちろん、食堂や清掃、警備などのビル管理に携わる全ての関係者にも解放されており、自由に出入りが可能な点です。また、フロア内の飲食店舗では、四季折々の豊かな食材が使われた健康的な料理を、無機質なプラスチックのトレーではなく、温かみある木の器で提供しています。
このウェルビーイングフロアは、在宅勤務やリモートワークでは得られない価値を入居テナントとビル関係者に提供しています。その主な価値の一つが、連帯感やコミュニケーションの促進です。入居テナントやビル関係者が企業や立場を超えて同じ空間で共生し、肩を並べて食事や仕事をするだけでも、自然と共感や連帯感が生まれやすくなります。
その上でこうした場があると、コミュニティの形成が促進されます。人間は元来、社会的存在であり、コミュニティがあるからこそ生き生きと毎日を送ることができます。事実、このフロアではテナント企業間の交流会やイベントが頻繁に開催されており、ビル内コミュニティの形成にも大いに役立っていると聞いています。こうしたコミュニケーションの充実は働きがいやエンゲイジメント向上を促し、時には新たなアイデアの創発やビジネスの接点につながるでしょう。
昨今、建物の環境性能を評価・認証する制度や仕組みは多く、それらが賃料上昇などの経済価値に繋がることが明らかになりつつあります。脱炭素への取り組みなど、企業は今後さらに対応が求められることでしょう。しかし、その一方で、従業員のエンゲイジメント向上やウェルビーイングの増進といった、数値には表れにくい価値が、今後の企業の長期的成長を支える重要な要素になるはずです。自社のオフィス戦略を練る際や、ビルオーナーとしてテナントを募る際、この観点を踏まえた取り組みをおすすめしたいです。
とはいえ、自社ビルを所有する企業よりもテナントとしてオフィスビルに入居する企業のほうが多いですし、予算や人材にも限りがあります。また、組織文化や歴史的な文脈も異なるため、企業ごとにオフィスづくりのあるべき姿は異なるでしょう。こうした中、オフィスづくりをリードするファシリティマネジャーは、自社に適したオフィスのあり方をどのように見出していけばよいのでしょうか。
私はファシリティマネジャーを「経営層の意思を自社オフィスに落とし込み、そして伝搬を推進する代弁者」だと捉えています。自社がめざすべき姿や実現したいビジョン、組織が全うすべきミッションなど、経営層の意思を汲み取り、オフィスという物理的な空間に落とし込んでいくという、重要な役目を担っているからです。そのため、常日頃から経営層とコミュニケーションをとるのはもちろん、プレスリリースなどの対外的に発信される情報にも目を通し、経営層の意思を自分なりに噛み砕いて理解することが重要です。
また、対外的な露出や評価が従業員のオフィスへの愛着を醸成することもあるため、オフィスを広報物に掲載したり、外部機関のオフィス賞などに応募したりするのも、有効な施策です。例えば、テレビCMの撮影に自社オフィスが利用されれば、世の中にも広く認知されて、従業員が愛着を持ってオフィスを利用するようになるかもしれません。
その一方で、オフィスが従業員に利用される以上、その価値を正しく伝えていくのもファシリティマネジャーの役割だと思います。オフィスづくりを進めるうえで、従業員からの不満やクレームは付き物です。もちろん、ユーザーである従業員の声は真摯に受け止めるべきでしょう。しかし、その声に耳を傾けすぎてしまうと、本来意図したオフィスの使い方から乖離し、経営層の意思を受けたコンセプトを毀損するおそれもあります。クレームは真摯に受け止めつつ、なぜこうした動線になっているのか、なぜこうした使い方ができないのかなどを丁寧に説明し、理解を得ることを心がけましょう。
人々の働き方が多様化する今、オフィスも姿を変えていく過渡期にあります。オフィスというリソースを活用して、いかに組織の成長を実現するのか、思案している経営層も多いはずです。ファシリティマネジャーはこの好機を逃すことなく、組織の先頭に立って、自ら思い描く「あるべきオフィスの姿」を具現化し、CREマネジメントによって企業のサステナブルでウェルビーイングな経営の一翼を担ってほしいと思います。
リサーチレポート集発行!
多方面の有識者からのヒントがここに。
最新データを今すぐダウンロード
NTTファシリティーズがお届けするメールマガジン『えふ・マガ』。
環境や建築、レジリエンスなどに関する社会動向を、有識者のインタビューやビジネスコラム、プロジェクト事例を通じて、日常やビジネスの現場で参考になる情報をお届けします。
お気軽にご登録ください。