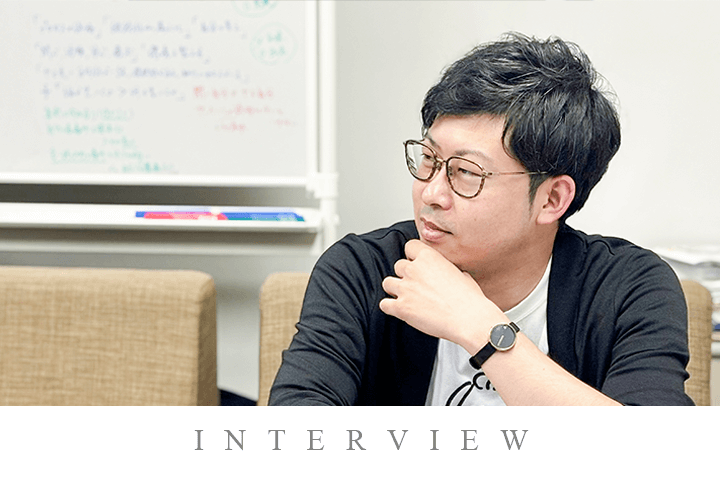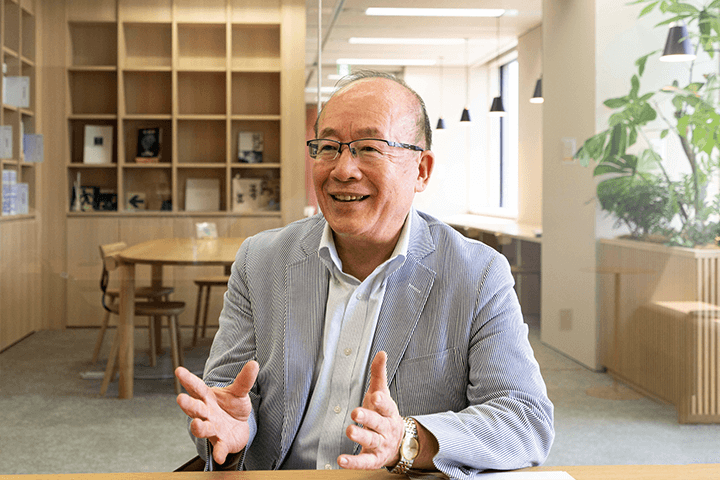コロナ禍以降、企業では社員を取り巻く環境の見直しが求められています。リモートワークやハイブリッドワークが定着した時代において、社員のエンゲイジメントを高め、組織の力を引き出すためには、どのようなワークプレイスやワークスタイルが必要でしょうか。名古屋市立大学大学院講師であり、人間科学の視点から働く場や働き方を研究している佐藤泰さんにお話を伺いました。
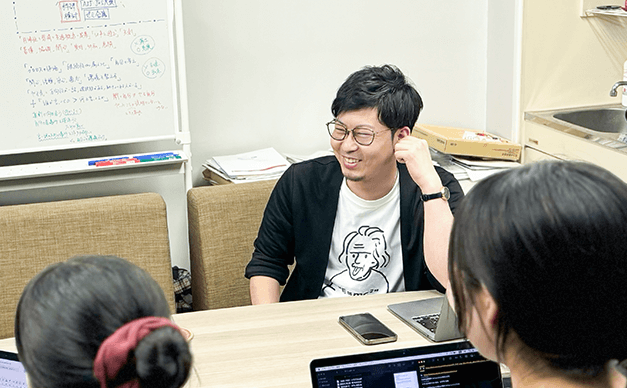
オフィス空間には「文脈」が不可欠
私は名古屋市立大学大学院芸術工学研究科の建築都市領域で、建築や人間科学を専門に研究活動を行っています。
学生時代に学んだのは早稲田大学の人間科学部です。実家が設計事務所を営んでおり、子供のころから建築や設計に親しんでいたのですが、その一方で「人間が認知する空間」にも強い関心がありました。「人間が認知する空間」とは、私たちが目や耳を通じて主観的に把握する空間のことです。
建物を建てる際には設計図が作成され、それを通じて人間は空間の全体像を把握します。しかし人間が主観的に把握する空間は、設計図に描かれた情報だけでは表現できない要素があります。それは、人間の五感によって認知される広さや高さ、色調、音響、匂いなどの要素です。
つまり、建築物や空間について深く考察するためには、設計図のような鳥瞰的視点だけでなく、人間の認知を起点とした、よりミクロな虫瞰的(ちゅうかんてき)視点が必要です。そして、後者の視点から深く掘り下げるには「人間とは何か」を突き詰めなければいけません。こうした問題意識から、私は建築や設計などと同時に「人間とは何か」を考える学問分野である人間科学を専攻しました。
現在の主要な研究テーマは「人間科学の視点からみた『はたらく場』『はたらき方』研究」です。これは「社員の文脈から考えるワークプレイス研究」とも言い換えられます。ここでいう「文脈」とは、「私たちの振る舞いの集合とその応答によって築かれるもの」と定義しています。文脈とは人々の「主観の集合」であり、より良いオフィスや働き方を構築するには、その集団における「主観の集合」を適切に捉え、理想的な形に変化させていく必要があると考えています。
例えば「オフィスにリフレッシュスペースを設けたがうまく利用されていない」といった問題をしばしば耳にします。これに限らず、空間の用途やルールを掲示していたとしても、設置した施設が狙い通りに利用されないケースは多いものです。他方で、例えば図書館の自習室を訪れると、自然と私語を慎み、静かにする人は多いと思います。
この違いを生んでいるのが「文脈」です。私たちは子供のころからの教えや経験と習慣によって、「図書館の自習室では静かにするもの」という文脈を自然と共有しています。そのため、誰かに特別な指示を受けなくても、静かに自習室を利用できるのです。
しかし、多くの企業では、こうした文脈をうまく構築できていないことがあります。もし先進的で快適な施設を設置していたとしても、それらを使いこなせる文脈が構築できていなければ、使用方法やルールの説明があったとしても当初の狙い通りには利用されず、十分な効果は得られません。このような現象について、「物理的環境は文脈を超えられない」と講義や講演などでお話しすることもあります。
では、文脈はどのように構築すればよいのでしょうか。その答えは「コミュニケーションの積み重ねによるボトムアップ式の合意形成」に他なりません。文脈とは主観の集合であるため、社員の一人ひとりがコミュニケーションを積み重ねながら合意を形成し、それぞれの主観を擦り合わせながら構築しなければいけません。企業でオフィスづくりを担う方の役目は、この合意形成を促進し、リードすることといえるでしょう。
理想のワークプレイスづくりには多様な取り組みが必要
上記を踏まえて、社員のエンゲイジメントを高め、組織の力を最大限に引き出すワークプレイスを構築するには、どのような施策や取り組みが求められるでしょうか。
まず、人間科学的な観点から優れたワークプレイスを定義すると、「心理的安全性とワークエンゲイジメントが担保され、社員がその集団の一員であり続けたいと思う集団凝集性があり、コミュニケーションが活発なオフィス」といえます。心理的安全性の確保が、社員のエンゲイジメントを高まることや、コミュニケーションの促進によってイノベーション創発に繋がることは、多くの研究からも明らかです。こうしたワークプレイスを築くには、ソフト面やハード面の施策はもちろん、社員の行動やマインドにも働きかける幅広い取り組みが必要になります。
例えば、オフィスの物理的環境は「ビュッフェ的」であることが望ましいと考えています。ビュッフェには肉、魚、野菜など複数のジャンルの料理が並び、多種多様なメニューの中から好きな料理を選べます。これと同様に、オフィスも社員一人ひとりが思い思いの方法でスペースを利用できるのが理想です。執務やコミュニケーションを想定したスペースであれば、さまざまな種類のデスクやイス、ソファ、マットなど、社員が多様な姿勢や気分で仕事ができる環境を整備するとよいでしょう。
近年増えてきている「ABW(Activity Based Working:社員が働く場所を自由に選択できる働き方)」と似た考え方ですが、ABW的な運用において、各空間の用途・運用を厳格に定めてしまう事例も見受けます。これに対し、この「ビュッフェ的なオフィス」という表現は、その空間をどの用途で使うべきかをあまり厳格には定めず、社員それぞれが思い思いの用途や方法で使用してよいのだ、というメッセージを伝えたい意図があります。
この施策の目的は、社員一人ひとりがオフィスにおいて多様な働き方ができる選択の自由度を守ることで、心理的安全性やエンゲイジメントの醸成を図ることです。実際に設けられる設備や什器の数には限りがありますが、出来るだけ画一的でない空間をめざすのがポイントだといえます。
また、こうしたオフィスにはフリーアドレス制などと同様に、社員同士の関係性を攪拌してコミュニケーションを促進する効果もあります。しかし、コミュニケーションの促進にこだわるあまり、例えば「一日一回はコミュニケーションスペースを利用しましょう」といった規則を設けてしまうと、社員の選択肢が逆に狭められ、心理的安全性などが損なわれる恐れもあります。そのため、環境を押し付けすぎることなく、あくまで社員の好みや気分を尊重することも大切です。
ただし、先ほども述べたとおり、環境を整備するだけでは理想のワークプレイスは構築できません。オフィスのさまざまなスペースが有効に利用され、コミュニケーションが活性化するためには、仕組みづくりやアクティビティの企画が必要不可欠です。例えば、成果主義企業の中には、自身の成果に直結しない同僚とのコミュニケーションが避けられてしまう場合があります。しかし、それでは組織内の人間関係は希薄になり、有意義な情報を獲得できるチャンスの損失につながりかねません。そのため、業務に関係する勉強会を開催し、グループワークを実施するなどして、インフォーマルなコミュニケーションに依存しない交流機会を創出する工夫が必要です。
加えて、最近の若手社員はコロナ禍に学生生活を送った影響もあり、年齢や属性の異なる相手とのコミュニケーションに負荷を感じやすかったり、職場における関係性構築を敬遠しがちな傾向があります。そのため、ハイブリッドワークを導入している企業であれば「なぜオフィスに出社してほしいのか」「様々な同僚とのコミュニケーションにどんな意味があるのか」といったことを、丁寧に言語化して説明することも重要だと思います。
その他にも、上司や同僚たちとの関係性を構築するアクティビティを企画して、無理のない形で職場における人間関係を醸成していく必要があるでしょう。かつてはノンバーバルなコミュニケーションの中で伝達できていた事柄かもしれませんが、若手社員の活性化を図るためにも、メッセージをしっかりと言語化して伝えていくことが大切なのです。
社員を「追いかけすぎない」ことも大切
このように理想的なワークプレイスを構築するには、ハードとソフト、言語と非言語、自由と強制など、さまざまな対立する要素を調整し、社員たちとコミュニケーションを取りながら施策を実践していかなければなりません。その長期的な取り組みの先に、それぞれの企業に適した文脈が構築されるはずです。
しかし、こうした長期的な取り組みを実践するのは、なかなかに骨が折れます。特に、オフィス施策を担当する方には大きな負担になるはずです。私もワークプレイス構築や運用改善に関する実務に携わることがありますが、多種多様な施策を企画し、実践し、継続することの難しさを痛感します。
そのため、私はワークプレイス構築や運用改善に際して、2つのことに気を付けています。1つ目は、短期間で得られる成果を継続して挙げることです。それぞれの企業に適した文脈の構築は長期戦のため、目標達成までの道のりが長く、焦りやモチベーションの低下に繋がりがちです。これが積み重なると取り組み自体が頓挫しかねません。だからこそ、小さなことでもよいので短期的な目標を設定して、一つひとつの目標をクリアする喜びを感じられる仕組みを作ってみましょう。
そして2つ目は、社員を追いかけすぎないことです。せっかく施設を設けたのにあまり利用されなかったり、施策を企画したのに周囲が乗り気でなかったりすると、担当者はつい社員を「追いかけて」しまいがちです。その焦りや責任感は理解していますが、取り組みを浸透させようとルールを設けたり、社員の行動を縛ったりすると、心理的安全性が低下するなど逆効果にもなりかねません。そのため、一部の社員が乗り気でないならその理由を尋ね、対策は打ちながらも、気長に行動変容を待つとよいでしょう。
いずれにせよ、組織は一人ひとりがポジティブで積極的でなくてはうまく機能しません。ワークプレイスや文脈の構築に取り組むのであれば、まずは「社員が前向きに働けるようになるには、どうすればよいのか」という点を意識して、各種施策を立案・実践していくことが重要だと思います。
Research Report資料ダウンロード
リサーチレポート集発行!
多方面の有識者からのヒントがここに。
最新データを今すぐダウンロード
Newsletterえふ・マガ登録
NTTファシリティーズがお届けするメールマガジン『えふ・マガ』。
環境や建築、レジリエンスなどに関する社会動向を、有識者のインタビューやビジネスコラム、プロジェクト事例を通じて、日常やビジネスの現場で参考になる情報をお届けします。
お気軽にご登録ください。