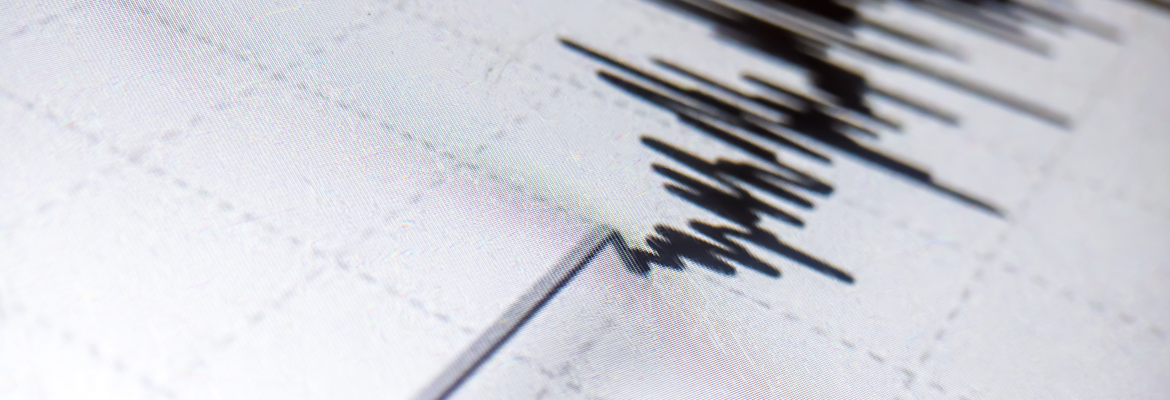関東大震災からはじまり、その後の度重なる震災経験を経て都市の形や機能が大きく変化しました。今後も首都直下型地震や南海トラフ地震など巨大地震の発生が予測されています。ここでは、過去の震災およびその後の復興対策からひも解く「防災都市」づくりについて解説します。
後世に残る復興都市計画
 1923年9月1日の正午2分前、相模トラフを震源とするマグニチュード7.9(推定)の地震が発生。関東大震災と命名されたこの地震は東京、神奈川、千葉などに甚大な被害をもたらしました。有史以来、たびたび大震災に見舞われている日本ですが、関東大震災は明治以降近代化が進んだ都市を襲った初めての大地震でした。都市の近代化が進む一方、市民の暮らす住宅は木質構造のものがほとんどで、その多くが密集していました。被害状況としては、揺れによる倒壊に加え、ちょうど昼食時間帯と重なったことが影響し、多くの火事が発生、大規模な延焼火災に拡大しました。
1923年9月1日の正午2分前、相模トラフを震源とするマグニチュード7.9(推定)の地震が発生。関東大震災と命名されたこの地震は東京、神奈川、千葉などに甚大な被害をもたらしました。有史以来、たびたび大震災に見舞われている日本ですが、関東大震災は明治以降近代化が進んだ都市を襲った初めての大地震でした。都市の近代化が進む一方、市民の暮らす住宅は木質構造のものがほとんどで、その多くが密集していました。被害状況としては、揺れによる倒壊に加え、ちょうど昼食時間帯と重なったことが影響し、多くの火事が発生、大規模な延焼火災に拡大しました。
関東大震災後、日本政府はその被害の甚大さを教訓に都市の復興に乗り出します。その中心となった人物が、その年の4月まで東京市長を務めていた後藤新平でした。東京市長在任中に、重要街路整備や街路工作物の整理、公園や広場の整備、港湾インフラの拡充などといった16の事業を盛り込んだ「東京市政刷新要綱」を推進しますが、残念ながらこの構想は実現しませんでした。
しかし、震災翌日の9月2日に発足した第二次山本権兵衛内閣で、後藤新平は内務大臣に就任しただけでなく、内務省に設置された帝都復興院の総裁にも就きました。そして直ちに「帝都復興根本策」を立案します。その主な内容は遷都の中止、復興予算を30億円とする、欧米の最新の都市計画を採用したうえで日本に相応しい新都を作る、新都市計画実現のために地主に対して断固とした態度を取るというものでした。
当時の国家予算が約14億円とされる中で、「復興予算30億円」というのは非現実的であり、その規模は大幅に縮小されました。しかし、規模が縮小されたものの、東京中心部においては、現在の昭和通りのように防火帯となる幅の広い完全道路が多く設置され、墨田川には崩落した木造の橋に代わり、政府により整備された両国橋、東京市が整備した永代橋など、鉄骨の橋梁が何か所も新設されています。また、避難所となる大きな公園も相次ぎ整備され、学校の鉄筋コンクリート化も関東大震災の復興が契機となり推し進められました。こうした復興都市計画は東京だけではなく、同じように被害を受けた横浜でも進められています。
後藤新平らがまとめた政府原案での予算規模は15億円でしたが、最終的には4億7,000万円程度に縮小され、防災対策が十分とは言えない領域が残ったことは否定できませんが、後世に残る“復興に向けた都市計画”として成功した面が大きいと評価されています。
頻発する震災に対応できる基準の策定
 その後も日本ではたびたび大震災が発生しています。1944年12月に遠州灘を震源とする、マグニチュード7.9の昭和東南海地震が発生し東海地方に大きな被害をもたらしました。また、1945年1月には三河湾を震源とするマグニチュード6.8の三河地震が発生しています。これらの震源域では、それより90年ほど前にも同じような巨大地震が発生しており、それが「南海トラフ地震」の発生を予測する根拠となっていると言われています。
その後も日本ではたびたび大震災が発生しています。1944年12月に遠州灘を震源とする、マグニチュード7.9の昭和東南海地震が発生し東海地方に大きな被害をもたらしました。また、1945年1月には三河湾を震源とするマグニチュード6.8の三河地震が発生しています。これらの震源域では、それより90年ほど前にも同じような巨大地震が発生しており、それが「南海トラフ地震」の発生を予測する根拠となっていると言われています。
1995年1月17日早朝、淡路島北部を震源とするマグニチュード7.3の地震が発生しました。この阪神・淡路大震災は、当時テレビを主としたメディアを通じて、高速道路の高架橋崩落やビルの倒壊現場など被害状況が映像を交えてリアルタイムに伝えられたことで、改めて大地震の怖さが認識されました。阪神・淡路大震災では住宅の全壊が約10万5,000棟、半壊が14万4,000棟にも上りました。
この甚大な被害を受けて、住宅の耐震基準の見直しが進められます。耐震基準とは、地震に耐える構造の基準のことを言い、建築物を設計する際に最も重視されるものです。この耐震基準は大きな震災が起こるたび、人命の安全確保や二次災害の防止、建物の設備機能の維持を目的に改正されています。阪神・淡路大震災時には「旧耐震基準」(1981年5月31日までの建築において適用されていた基準。翌日の6月1日から適用されている基準を「新耐震基準」と言います)で作られた住宅の被害が大きかったことから、木造住宅に対し柱や梁などの部材の接合部に金物を配置することや耐力壁を設置することなどが盛り込まれた「新・新耐震基準」が2000年から施行されました。
そして、2011年3月11日に発生したマグニチュード9.0の東日本大震災では、住宅倒壊による被害は比較的小さく、しかしながら沿岸部での津波による被害が甚大でした。さらに2016年4月14日にはマグニチュード6.5の熊本地震が発生、住宅の損傷に加えて山崩れといった被害が発生しました。その後、2018年9月6日に発生したマグニチュード6.7の北海道胆振東部地震では各地で山崩れが発生したほか、苫小牧の発電所の停止をきっかけに北海道内の電力網のバランスが崩れ、北海道全域で停電が発生、日本で初めての「ブラックアウト」が起きました。このブラックアウトにより、交通網や様々な産業、医療分野などのあらゆる都市機能が停止するリスクが現実として起きることが判明しました。
不測の事態に備える「防災都市」づくりに向けて
 このような様々なリスクに対応できる都市づくりとは、不測の事態に備え、災害から都市を守り、被害を最⼩化することです。そのためには、ハードの整備(建築物の耐震化・耐浪化・不燃化、道路・橋梁・上下⽔道等の耐震化・強化等)とソフトの施策(消⽕・避難・救助等の「⾃助」、「共助」、「公助」)の⼀体的な取り組みの強化が必要となります。
このような様々なリスクに対応できる都市づくりとは、不測の事態に備え、災害から都市を守り、被害を最⼩化することです。そのためには、ハードの整備(建築物の耐震化・耐浪化・不燃化、道路・橋梁・上下⽔道等の耐震化・強化等)とソフトの施策(消⽕・避難・救助等の「⾃助」、「共助」、「公助」)の⼀体的な取り組みの強化が必要となります。
今後発生が想定される災害としては、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島南側の海域、土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレートおよびユーラシアプレートが接する溝状の海底地形を形成するいわゆる「南海トラフ」を震源とする巨大地震です。今後10年で30%程度、30年以内は70~80%の確率で発生するとされており、南海トラフ地震による影響範囲は、関東から九州地方までの広い範囲にわたり、大きな揺れや津波が押し寄せることが予測されています。
一方、首都直下型地震は今後30年以内に70%程度の確率で発生すると言われています。2015年に「首都直下型地震緊急対策推進基本計画」がまとめられ、首都中枢機能の確保や耐震化と火災対策、道路交通麻痺対策、膨大な数となる避難者や帰宅困難者などへの対策が示されています。東日本大震災の際には、直接的な被害が少なかった東京周辺でも、鉄道がすべてストップしたことで膨大な帰宅困難者が発生しました。主要道路も渋滞し、車での移動もできず、多くの人が数時間をかけて徒歩で帰宅したほどです。電力は確保されていたものの、通信の集中で携帯電話がつながりにくい状況も起き、安否確認にも苦労しました。
当時の教訓から、例えば公共施設や大規模商業ビル、都心部のマンションなどでは帰宅困難者を受け入れる体制の整備、各企業は社員の安全確保のため、入居するビルが安全ならば帰宅させず会社に留め置くという方針を打ち出すケースも出ています。併せて震災直後のサプライチェーンの確保といったBCP対策にも注目が集まり、多くの公共機関、企業がその対策を講じています。
9月1日は関東大震災から100年。阪神・淡路大震災や東日本大震災の教訓を生かして、各地の避難訓練もより大きな規模で、かつ実践的に行われています。今夏、各地で発生した豪雨災害でも「命を守る行動を」と繰り返し言われています。「天災は忘れた頃にやってくる」という警句がありますが、常々天災が起きることに留意して、社会インフラの対策も個人の対策も、絶え間なく進めていかなければなりません。自分たちの日々の生活、自分たちの安全を守ることが防災であることを意識して、一人ひとりが都市づくりに取り組む意識(自助)を持つことが、これからの防災都市に必要なことではないでしょうか。
関連する記事
メールマガジンで配信いたします。