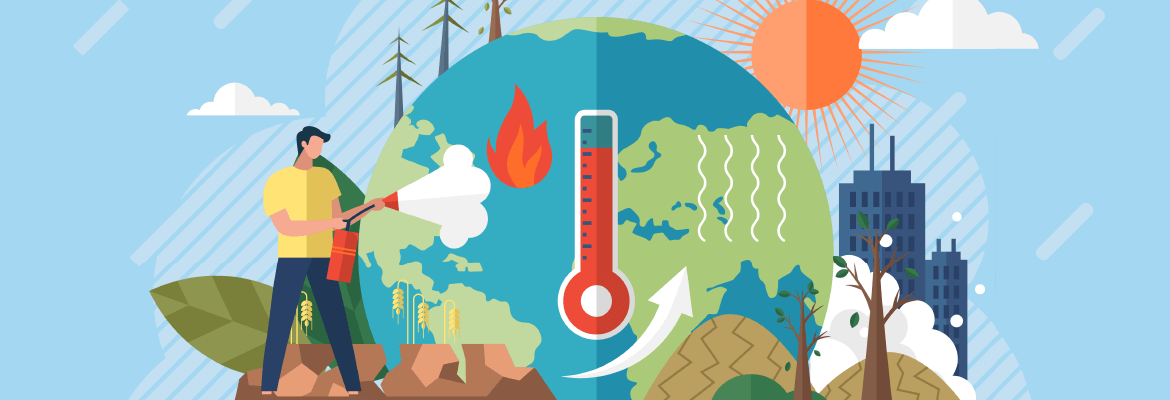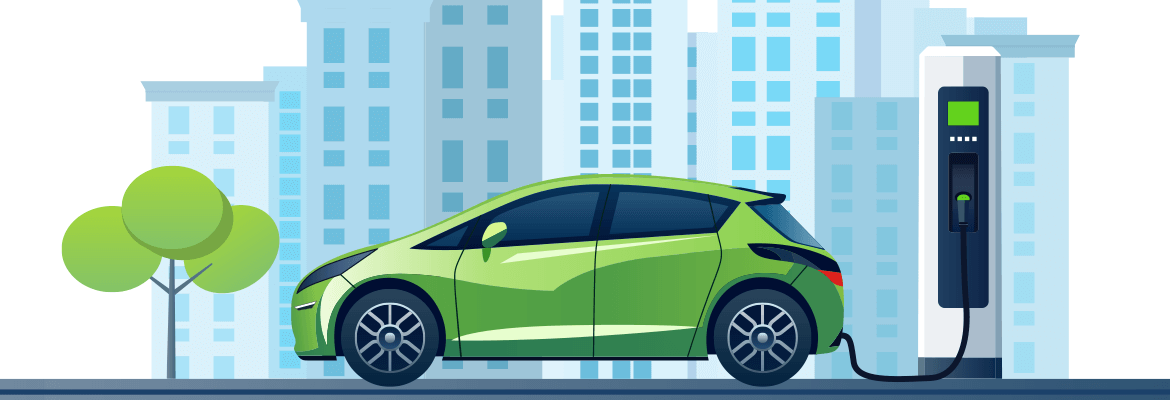地球温暖化対策の一環として、ジェット旅客機の燃料に廃食油などから作られたSAF(Sustainable aviation fuel=持続可能な航空燃料)を使用する動きが広がっています。今回は、従来の化石燃料に代わる次世代燃料として期待されるSAFの可能性と、未来に向けた展望を解説します。
航空を変えるSAFとは
 SAF(サフ)は「Sustainable aviation fuel」の略称で、持続可能な航空燃料を意味します。従来使用されている石油由来のジェット燃料と比べ、CO₂排出量を大幅に削減できるとされ、ジェット旅客機にSAFを活用する動きが広がっています。SAFは、植物や藻類、食品工場などから排出される植物由来の廃食油を原料に精製されるため、燃焼させても植物が光合成によってCO₂を吸収する特性から、実質的にCO₂の排出がほぼないとしています。また、原料として廃プラスチックや古紙も利用できるため、廃棄物を減らし資源の有効活用をめざす経済の仕組み「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」の構築にも大きく貢献すると言われています。
SAF(サフ)は「Sustainable aviation fuel」の略称で、持続可能な航空燃料を意味します。従来使用されている石油由来のジェット燃料と比べ、CO₂排出量を大幅に削減できるとされ、ジェット旅客機にSAFを活用する動きが広がっています。SAFは、植物や藻類、食品工場などから排出される植物由来の廃食油を原料に精製されるため、燃焼させても植物が光合成によってCO₂を吸収する特性から、実質的にCO₂の排出がほぼないとしています。また、原料として廃プラスチックや古紙も利用できるため、廃棄物を減らし資源の有効活用をめざす経済の仕組み「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」の構築にも大きく貢献すると言われています。
ガソリンなどを使用するレシプロエンジンは、特定の揮発性を有する燃料が必要であり、その品質によって燃焼効率や性能面に大きく影響します。一方ジェットエンジンは連続燃焼という燃焼方式の特性から、より幅広い性質や状態の燃料を受け入れることができます。一般的にジェットエンジンに使用される燃料は、灯油と同じ石油由来の「ケロシン」と呼ばれるものです。SAFは、このケロシンと化学構造がほぼ同じになるように精製されており、たとえば廃食油や廃プラスチックを使った場合でも、最終的にはケロシンと同等の燃料になります。そのため、既存のジェットエンジンや燃料供給設備をそのまま使うことができるのが大きな特長です。
しかし、その特長を活かしSAFを普及させるには、多くの課題が残されています。石油由来のケロシンは、大量生産が可能なため、調達コストを比較的低く抑えることができる一方、SAFは原油を採掘する必要がないという利点はあるものの、廃食油を原料とする場合には、食品工場やホテル、レストラン、家庭などから効率よく回収する仕組みの整備が不可欠です。そのため、原材料の安定した調達にはまだまだ課題があると言えます。また、石油から生成されるケロシンは品質が均一であるのに対し、SAFの原料となる廃食油や廃プラスチック、古紙は状態がまちまちであるため、そこから高品質な燃料を精製するには高度な技術が求められます。さらに、大規模な精製プラントの整備も必要となり、現時点ではSAFの生産コストはケロシンと比べるとはるかに高く、その点が普及の大きな障壁となっています。
SAF普及に向けた世界的な取り組み

航空ネットワークの発達は、人やモノ、情報の移動を加速させ、グローバル化を大きく後押ししてきました。現代社会の経済発展は、航空分野の貢献なしには成り立たないと言っても過言ではありません。しかし、地球規模でCO₂排出量の削減が求められる昨今、航空機という輸送手段へもその責任が問われています。こうした課題に対し、航空業界は積極的に向き合い、取り組みを進めています。
その一環として、2021年から国際航空のためのカーボンオフセットおよび削減スキーム(CORSIA)の運用が始まり、国際民間航空機関(ICAO)は、2024年以降のCO₂排出量を2019年の水準と比較して85%以下に抑えるという目標を定めています。こうした国際的な規制に対応し、継続的にCO₂排出量を削減していくためには、非化石燃料の活用比率を高めていくことが不可欠となっています。その最も有効な手段とされているのがSAFなのです。
しかし、2022年時点におけるSAFの世界供給量は約30万klとされ、これは全ジェット燃料のわずか0.1%程度にすぎません。国際航空運送協会(IATA)の試算によると、2050年までに航空分野でのCO₂排出量ネットゼロを達成するためには、約4.5億klのSAFが必要とされています。この目標に向けて、各国の航空会社は2030年までにジェット燃料へのSAF混合比率を10%にするという具体的な目標を掲げ、その導入を加速させています。
SAF利用が世界的に注目を集めるなか、その本格的な普及に向けて、原料調達の仕組みや生産技術のさらなる進化が求められています。こうした技術革新とコスト削減を同時に実現するため、欧州を中心に、石油大手各社がSAFの増産に取り組み、需要の高まりに応えるべく新たな生産計画を続々と発表しています。日本国内でも石油元売り各社が相次いでSAF製造に参入しており、各社が公表している供給計画を合算すると、2027年には約90万klのSAFが生産される見通しです。
さらに、水素とCO₂を合成し製造するPtL(Power-to-Liquid)タイプなど多様な技術により新たなSAFが開発され、量産化に向けて積極的な検討が進んでいます。これらの技術は、従来のバイオマス原料とは異なるアプローチでSAFを製造するため、原料調達の課題を克服する可能性を秘めています。新たな原材料と技術開発が、SAFの安定供給とコスト低減を実現するための鍵となるでしょう。
国内でSAFを安定供給するための取り組み
 日本国内でSAFを安定的に供給するためには、海外に依存しない、国内で調達できる資源の活用が重要です。こうした背景から、国内でSAFの安定供給を実現するために、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、2017年に「バイオジェット燃料生産技術開発事業」を開始しました。この事業は、SAFの原材料調達から製造、供給、航空機での利用に至るまで、一貫したサプライチェーンの構築をめざしています。そして、2030年まで航空燃料に対して10%のSAF混合を実現するという商用化の目標も掲げています。
日本国内でSAFを安定的に供給するためには、海外に依存しない、国内で調達できる資源の活用が重要です。こうした背景から、国内でSAFの安定供給を実現するために、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、2017年に「バイオジェット燃料生産技術開発事業」を開始しました。この事業は、SAFの原材料調達から製造、供給、航空機での利用に至るまで、一貫したサプライチェーンの構築をめざしています。そして、2030年まで航空燃料に対して10%のSAF混合を実現するという商用化の目標も掲げています。
具体的な取り組みとしては、木質バイオマスや微細藻類から抽出した油脂をもとに精製する技術の研究開発が進められてきました。藻類は成長が早く、光合成によってCO₂を吸収する性質があるため、環境にも優しい資源として期待されています。その一環として、2020年から2023年3月にかけては、日本微細藻類技術協会(IMAT)が微細藻類由来のSAFを実用化するための拠点整備と技術開発を実施しています。このプロジェクトでは、効率的なSAF供給を実現するため、微細藻類の選定から培養技術の確立、製造工程の検討、さらには培養から生産までのCO₂排出量の評価などさまざまな観点から研究が行われています。
航空業界でCO₂排出量を削減する手段として、将来的には航空機の電動化や水素エンジンの開発なども期待されています。しかしこれらの技術を実用化するまでには、相応の時間がかかると見られています。今後もさまざまな原材料の活用が進んでいくと予想されるなか、すでに下水汚泥からSAFを製造するという革新的な技術開発に取り組んでいる企業も存在するなど、この分野には多くの可能性があると言えるでしょう。
数年後、世界中のジェット旅客機へ当たり前のようにSAFが活用され、私たちの空の旅は、より持続可能で環境にやさしいものへと変わっていくはずです。こうした大きな変革を実現するには、企業や政府の努力だけでなく、私たち一人ひとりの理解と行動も重要です。SAFについて正しく知り、導入している航空会社を選ぶことで持続可能な空の旅ができます。次世代へクリーンな空を届けるため、できることから一歩ずつ行動を始めてはいかがでしょうか。
関連する記事
メールマガジンで配信いたします。