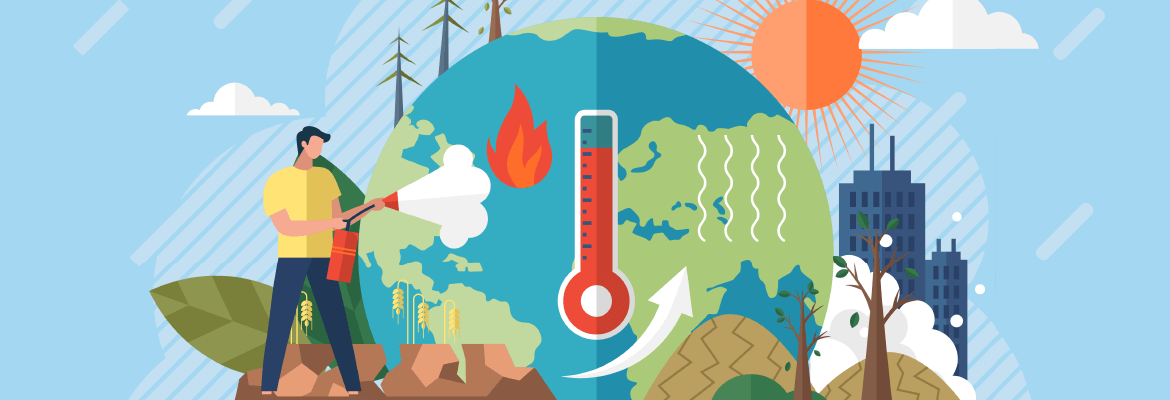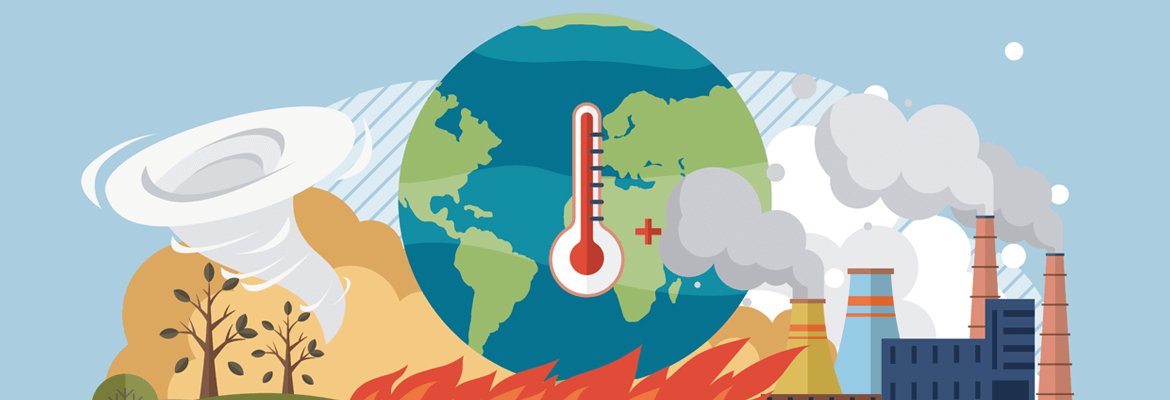世界気象機関(WMO)は2025年1月、2024年が観測史上最も暑い1年であったことを発表しました。日本でもその影響とみられる災害が発生しています。今回は地球温暖化が与える影響や世界各国の取り組みなどについて解説します。
地球温暖化の転換点となった2024年
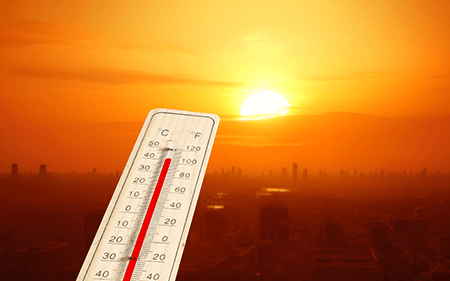 2025年1月、世界気象機関(WMO)は年次報告書において、2024年の世界平均気温が産業革命前の水準と比べ1.55℃上昇し、観測史上初めて1.5℃を上回ったと発表しました。この1.55℃という結果は、2015年に国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)で採択された地球温暖化防止の国際的な枠組み「パリ協定」で掲げる、1.5℃という気温上昇目標を単年で初めて超過したことになります。一方、気象庁のデータによると、日本の2024年平均気温上昇は1.48℃であり、パリ協定の目標は上回っていないものの、それに迫る上昇幅を記録しています。
2025年1月、世界気象機関(WMO)は年次報告書において、2024年の世界平均気温が産業革命前の水準と比べ1.55℃上昇し、観測史上初めて1.5℃を上回ったと発表しました。この1.55℃という結果は、2015年に国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)で採択された地球温暖化防止の国際的な枠組み「パリ協定」で掲げる、1.5℃という気温上昇目標を単年で初めて超過したことになります。一方、気象庁のデータによると、日本の2024年平均気温上昇は1.48℃であり、パリ協定の目標は上回っていないものの、それに迫る上昇幅を記録しています。
WMOは1950年に設立され、2024年3月現在、世界193の国と地域が加盟する国連の専門機関です。各国の気象庁などと連携し、観測データの収集や分析を行うほか、気候変動によるリスクを評価し警戒情報を発信するとともに、目的に応じた気象情報の提供を通じて、世界各国における防災体制の整備などへ貢献しています。なお、地球温暖化に関する報告書などで私たちが目にする気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、このWMOと国連環境計画(UNEP)が1988年に設立した国際的な組織です。
2024年の世界における年平均気温は、基準値である1991年から2020年の30年平均値より0.62℃上昇し、1891年の調査開始以降で最も高い記録となりました。さまざまな要因で変動を伴いながら長期的には100年で0.77℃上昇していると報告されており、これは地球が着実に温暖化している傾向を示しています。
そして、これらの影響により、近年さまざまな自然災害が発生しています。2024年の年次報告書では、干ばつや山火事といったリスクがこれまでにないほど高まっていることに加え、特定の地域では「季節外れ」の現象が増加していることも指摘されています。
地球温暖化が引き起こす自然災害とリスク

2025年1月、米国カリフォルニア州ロサンゼルス近郊で発生した山火事は、住宅地にも延焼し、多くの被害を出す深刻な事態となりました。鎮火までに20日以上を要し、延焼面積が拡大したことで被害総額は1,640億ドルを超えたと言われています。山火事が拡大した背景には、異常な乾燥とサンタアナ風と呼ばれる強風が大きく影響したと考えられています。2024年の夏から秋にかけての異常な高温と、11月から12月にかけて降雨がほとんどなく植生の乾燥が深刻化したこと、2025年1月7日に過去10年で最も強力なサンタアナ風が吹き、火災の延焼を助長したことが被害の拡大につながったと分析されています。
そして、日本でも同様に山火事が発生しています。2025年2月26日に岩手県大船渡市の山林で発生した火災は、4月7日にようやく鎮火が確認されました。焼失面積は約2,900haに達し、平成以降で最大規模の山火事となりました。同じ頃、岡山県岡山市や隣接する玉野市でも山火事が発生、山梨県大月市では山林約150haが焼失するなど、異常な乾燥と強風が原因とみられる大規模火災が各地で相次ぎました。
このような乾燥や強風といった異常現象の背景には、地球温暖化に伴う気候変動が複合的に影響していると考えられています。気候変動に関するIPCCの第6次評価報告書をはじめとする研究結果は、温室効果ガスの排出増加が地球の平均気温を上昇させ、降水パターンの変化、極端な高温、干ばつ、強風などを引き起こす可能性を高めている事実を示唆しています。
また、こうした地球規模での長期的な気温上昇は、南極と北極を形成する氷の状態に深刻な影響を与えることが懸念されています。南極域における海氷面積は、2020年までは大きな変化がないとされてきましたが、2020年以降、減少傾向が観測され、特に2023年および2024年は過去最小の海氷面積を記録しています。2023年1月には、南極のブラント棚氷から東京23区の2.5倍に相当する約1,550㎢の氷山が分離し、南氷洋を漂いはじめました。これは気温が平年よりも2℃以上高い状態が続いたことが一因ともみられています。
北極域でも同様に、1979年の衛星観測開始以来、年平均で約8.5万㎢、つまり北海道に匹敵する広さの海氷が減少し続けており、地球温暖化の深刻な影響を象徴する現象とし注目されています。一方で、海氷面積の縮小から、これまで氷に覆われ航行が困難だった海域が、新たな船舶輸送ルートとして開拓される可能性もあり、異なる話題を集めています。また、北極域における手つかずの石油、天然ガス、鉱物といった地下資源へのアクセスも容易となることから、資源開発に伴う海洋汚染や、開発活動による騒音、生態系の破壊といった、脆弱な北極域生態系への負荷や環境汚染のリスクが懸念されています。
持続的な自然エネルギーが拓く未来
 こうした地球温暖化の進行に対処するためには、各国が連携して取り組みを進めることが不可欠です。パリ協定に基づく協力体制に加え、再生可能エネルギーをはじめとする自然エネルギーは、温室効果ガス排出量を大幅に削減し、持続可能な社会を実現するうえで欠かせない要素として世界中で注目を集め、その普及、活用を促進するためのさまざまな国際協力が進められています。
こうした地球温暖化の進行に対処するためには、各国が連携して取り組みを進めることが不可欠です。パリ協定に基づく協力体制に加え、再生可能エネルギーをはじめとする自然エネルギーは、温室効果ガス排出量を大幅に削減し、持続可能な社会を実現するうえで欠かせない要素として世界中で注目を集め、その普及、活用を促進するためのさまざまな国際協力が進められています。
地球温暖化の主な原因となる温室効果ガス(GHG)は、二酸化炭素(CO₂)のほか、メタン(CH₄)、亜酸化窒素(N₂O)、代替フロン、六フッ化硫黄(SF₆)などが対象になります。IPCCの調査によると、これらのGHGは、それぞれ温暖化への影響度が異なり、CO₂に換算してその影響が評価されています。驚くべきことに、大気中にわずか0.04%しか存在しないCO₂の排出削減が、地球温暖化対策における最重要課題の一つとなっているのです。
日本では、経済産業省が2025年2月に発表した「第7次エネルギー基本計画」において、太陽光や風力、地熱といった持続的な自然エネルギーの比率を2024年度には全体の約4割~5割に拡大する方針が打ち出されました。これら自然の力を活用するエネルギー源の導入促進に加え、民間の取り組みとしても家消費型の太陽光発電や電気自動車(EV)の普及が進み、社会全体でカーボンニュートラルへの取り組む意識が高まっています。
世界へ目を向けてみても、欧州連合(EU)は、2019年12月に発表した気候変動対策の包括的な政策「欧州グリーンディール」を中心に脱炭素を、中国では「2060年カーボンニュートラル」目標のもと、石炭火力発電の段階的廃止とEVの積極的導入を進めています。各国のこうした取り組みは、地球温暖化対策の強化につながる重要な動きと言えます。
1987年に採択されたモントリオール議定書において、オゾン層を破壊する原因となるフロン類など特定物質の生産および使用を段階的に削減し、全廃することが定められました。2023年、アメリカ航空宇宙局(NASA)とWMOが共同で発表した報告書によると、フロン類などの使用規制の結果、南極上空のオゾン層は2066年頃、北極上空では2045年頃、それ以外の地域では2040年頃に、1980年の水準まで回復すると発表されています。
地球温暖化対策もこのオゾン層回復のように、一人ひとりの選択と行動の積み重ねによって、確かな成果を生み出すことが可能になります。自然を活用したエネルギーの利用や省エネの工夫、持続可能なライフスタイルの実践など、日々の生活の中でできることは少なくありません。未来の世代により良い地球環境を託すために、今こそ私たち一人ひとりの意識と行動が問われているのでないでしょうか。
関連する記事
メールマガジンで配信いたします。