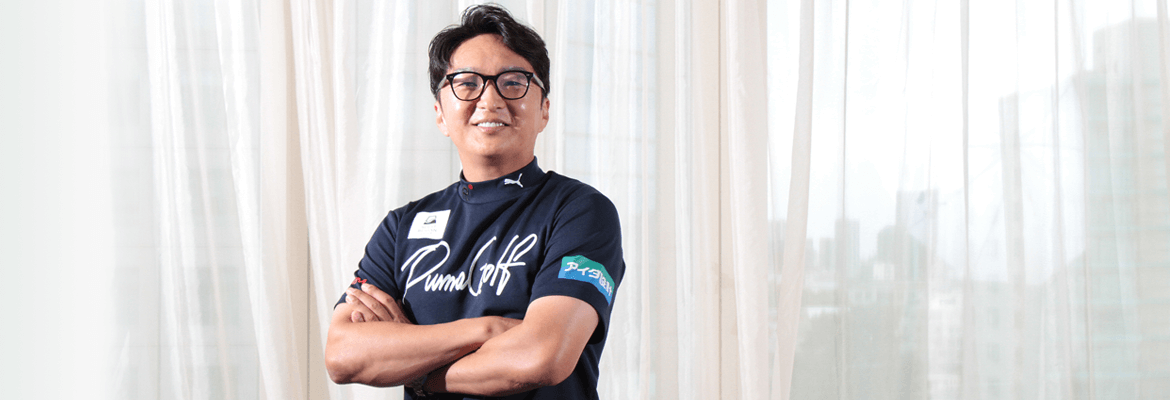前編では、ゴルファーそれぞれのニーズに寄り添うフィッティングの真髄や、クラブを渡してからが“本当のフィッティングの始まり”という小倉氏の哲学について伺いました。後編となる今回は、アベレージゴルファーが陥りがちなクラブ選択の誤解や、情報過多な時代におけるクラブ選びの難しさについてお話を伺いました。
【プロフィール】
小倉 勇人(おぐら はやと)
1978年生まれ、東京都出身。学生時代からゴルフを始め、某有名ゴルフ誌の編集者としてキャリアをスタート。その後、ゴルフ雑誌やWEBを中心に編集・執筆活動を行いながら、クラブの専門知識とフィッティング技術を深め、クラフトマン、クラブフィッターとしても活躍する。現在は「株式会社リルガレージ」主宰として、アマチュアゴルファーが「自分に合ったクラブ」でゴルフを最大限に楽しめるよう、日々情熱を注いでいる。
正しいと思っていたことが、パフォーマンスを下げている?
 ――飛距離に悩みを抱えるシニアゴルファーが多くいらっしゃいます。解決策などはあるのでしょうか
――飛距離に悩みを抱えるシニアゴルファーが多くいらっしゃいます。解決策などはあるのでしょうか
年齢を重ねることで飛距離が落ちる主な原因は、筋力の低下よりも「関節の可動域が狭まること」にあります。長くゴルフを続けている方ほど、「パワーがある人は重く硬いシャフト(クラブのヘッドとグリップをつなぐ棒状の部分)を使うべき」というイメージを強く持っている傾向があります。しかし、現代のシャフトは大きく進化していて、パワーのある人もない人も、それぞれに合った“ちょうど良い重さや柔らかさ”が選べるようになっています。
多くの方が「重いクラブは振りづらい」と感じて、つい軽いクラブを選びがちですが、実はこれが落とし穴です。軽すぎるクラブは無意識のうちに力みを生みやすく、ミート率の低下やミスショットの原因になることが多いのです。ゴルフスイングは、ヘッドの遠心力を活かし再現性を高めるものですが、クラブが軽すぎると遠心力が不足し、結果的に力みによりスイング軌道が乱れてしまいます。
女性用クラブの多くが「レディース」表示の軽く柔らかいスペックになっていることも問題だと私は考えています。多くの女性ゴルファーが、この表示だけを基準に選ぶため、もっと飛ばせるはずなのに、軽すぎるクラブのため軌道が乱れ当たりが悪くなってしまいます。結果として、本来のポテンシャルを発揮できずに伸び悩んでいるのが現状です。これは、特定の層に向けて作られた製品であっても、その人たちの本当のニーズや秘めた可能性を必ずしも引き出しているとは限らない、ということを気づかせてくれます。
さまざまなスペックのシャフトが登場する近年、クラブの選択肢が大きく広がりました。しかし、「できるだけ楽に上達したい」という思いから、誤ったクラブ選びをしてしまうケースも増えています。ゴルフの飛距離を決めるのは、「ボール初速」「打ち出し角」「スピン量」からなる「飛ばしの3要素」と言われるもの。ヘッドスピードを上げるために軽いクラブを選ぶ方もいらっしゃいますが、打点が安定しなければ、どれだけヘッドスピードが出ても飛距離は伸びません。飛距離を伸ばすには、「安定して芯でボールをとらえる」ことが大切であり、そのためには自分の持つエネルギーとバランスの取れた重量を持つクラブが必要なわけです。この“適切な重量”こそが、ミート率を最大限に高める鍵となるのです。
加齢や四季の変化によって一時的に飛距離が落ちたとき、安易に軽いクラブへ買い替えることは非常にリスクがあります。というのも、軽いクラブに変えたことでミート率が下がり、飛距離が戻らなくなってしまう“負のスパイラル”に陥るケースが多く見られるためです。
実際、悩みを抱えてフィッティングに来られた方に、少し重めのクラブをお渡ししますと、最初は驚かれることがよくあります。しかし、試打していただくと「しっかり当たる」「飛距離が戻った」といった反応が多く、さらに驚かれます。たとえやや重く感じたとしても、それが適正な重さであれば、スイングの安定感が増し、結果的に良いパフォーマンスにつながるのです。
情報過多の時代における“1本を選ぶ”難しさ
 ――アマチュアゴルファーの方にとって、クラブ選びの基準は人それぞれだと思いますが、選択肢が多すぎて「何を選べばいいのか分からない」と感じることも多いのではないでしょうか
――アマチュアゴルファーの方にとって、クラブ選びの基準は人それぞれだと思いますが、選択肢が多すぎて「何を選べばいいのか分からない」と感じることも多いのではないでしょうか
おっしゃる通りです。私自身、長年ゴルフ業界に関わり、クラフトマンや雑誌記者として常に最新クラブに触れながら、技術トレンドの変化を肌で感じてきました。だからこそ実感するのですが、選択肢が増えた一方で「何を選べばいいのか分からない」と迷ってしまう方も増えているように見受けられます。私のように、ミニドライバー(通常のドライバーよりヘッドが小さくシャフトが短いクラブ)を自分好みにカスタマイズして楽しむような“自由な選び方”も可能になりましたが、アベレージゴルファーの方々にとっては、試打記事やYouTube、SNSなどにあふれる情報の中から、単に人気があるという理由だけでなく、“本当に合った1本”を見つけ出すことが、以前よりもずっと難しくなっていると思います。
ゴルフクラブ、特にドライバーの反発係数に関するルールは、2008年に大きな枠組み※が定められてから、すでに17年近く経過しています。このルールのもとでは、各メーカーが飛距離などの性能面で大きな違いを出すことが難しくなってきています。そのため、極端に「飛ぶクラブ」を開発することは現実的に難しく、メーカー各社は「魅力を感じてもらえるクラブ」に知恵を絞っているのが現状です。近年では、デザインや打感、打音といった感覚的な要素や、ミスショットへの寛容性などで個性を打ち出す傾向が強まっています。
具体的には、ミスショットでも飛距離のロスが少ない、つまり寛容性の高さや、余計なスピンを抑えてより遠くへ飛ばせるクラブヘッドの開発が進んでいるのが特徴的です。また、重心設計の進化によって打ちやすさを向上、新素材を取り入れることで、ルールの範囲内でフェース(打面)の反発性能を最大限に引き出す工夫がなされるなど、各メーカーがしのぎを削っている状況です。
一方で、ゴルファーの意識にも変化が見られるようになりました。私たちが若い頃は、グリーン周辺りでチップショットを行うお助けクラブ“チッパー”などは「カッコ悪い」と思われがちでしたが、今はそうしたチッパーやバンカー専用ウェッジ、エキストラクラブなどが注目を集めており、すぐに売り切れてしまうほど人気です。若い世代のゴルファーの中には「なぜ目上の世代の人たちは、こんなに便利で効果的なクラブをカッコ悪いと思うのだろう」と疑問に感じる人も増えています。こうした固定概念が薄れ、クラブ選びの自由度が広がっているのは、今のゴルフ界の大きな流れの一つであり、私自身にとってもとても新鮮でうれしい変化だと感じています。
※主要なゴルフ用具に関するルール改定(特にドライバーの反発規制)は、英国ゴルフ協会(R&A)と全米ゴルフ協会(USGA)によって段階的に導入され、完全施行されたのは2008年1月1日
信頼を生むのは、“言い切れる力”
 ―クラブ選びにおいて、フィッティングが重要とされるのはなぜでしょうか
―クラブ選びにおいて、フィッティングが重要とされるのはなぜでしょうか
ご自身のミスがスイングに原因があるのか、それともクラブにあるのかをはっきりさせたい方、また「どうすれば上手くなれるのかイメージがつかめない」と感じている方には、ぜひ一度フィッティングを受けていただきたいと思っています。自分では気づきにくい部分も、第三者であるクラブフィッターの視点からはしっかりと見えることが多く、そうした気づきが、上達へのヒントになります。クラブの買い替えを検討している方で、「せっかくなら今よりもっと自分に合ったクラブが欲しい」と思うのであれば、既製品のスペックだけで決めるのではなく、フィッティングを試してみることをお勧めします。
フィッティングをお勧めしますと、「仕事だからそう言っているのでしょ」と思われることもあります。しかし、ゴルフクラブに関する疑問や悩みを本気で解決したいのであれば、クラブフィッターこそが最も知識と経験を持っており、適切なアドバイスができる存在だと私は考えています。
―メーカー直営店やゴルフ用品店でも、フィッティングは受けられますが、小倉さんには、どんな強みやメリットがありますか
メーカーが行うフィッティングは、基本的に自社製品をより納得して購入していただくことが出発点です。それに対して、私のようなどこにも所属していないクラブフィッターは特定のメーカーに縛られることがない分、信用がなければお客様に選んでいただけません。メーカーやゴルフ用品店とは立場が異なるため、「より中立的な意見を聞きたい」「忖度のないアドバイスが欲しい」という方には、有料であっても価値を見出せていただけると自負しています。しがらみがないからこそ、本音の提案ができるのが強みです。
私自身、YouTubeなどでクラブの解説を行っていることもあり、「この人は色々なクラブを実際に試していて、知識も豊富だな」と感じていただける機会が増えているように思います。自分で打って確かめたクラブであればこそ、自信を持ってその特徴をお伝えできますし、性能についてもはっきりと言い切ることができます。この“言い切れる力”は、皆様に納得していただくうえで非常に大切だと考えています。
関連する記事
メールマガジンで配信いたします。