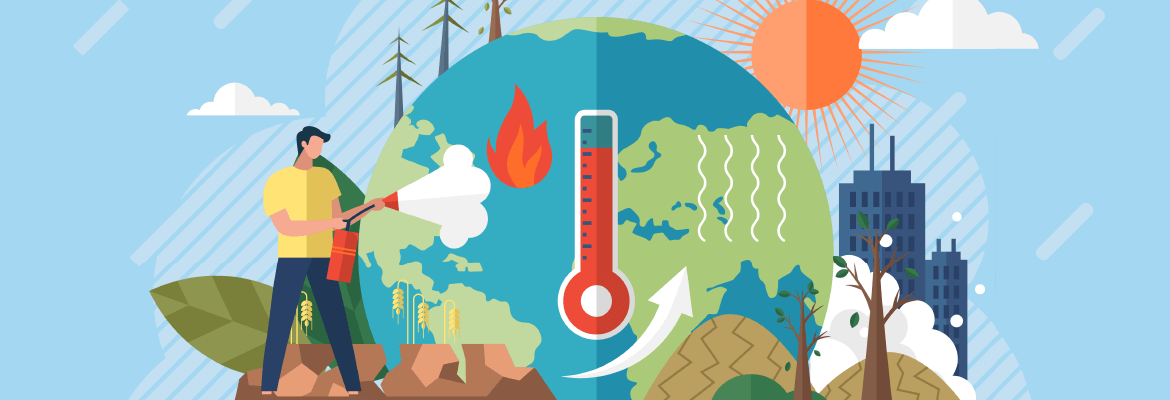GX(グリーントランスフォーメーション)の推進により、日本社会は脱炭素と経済成長の両立に向けた本格的な転換期を迎えています。その中でも、建物における省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの活用は、企業活動の中核を担う課題となっており、その取り組みは事業規模や施設の大小を問わず広がっています。今回は、建物における省エネ・再エネ活用、ESG経営など、これからの持続可能な社会に向けた取り組みを解説します。
GXが導く脱炭素社会と産業構造の転換
 GX(グリーントランスフォーメーション)とは、地球温暖化の原因となる温室効果ガス(GHG)排出の抑制を目的に、化石燃料の使用を減らし、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを活用した経済や社会への転換を推進する取り組みです。社会全体の構造を変えるこの活動は、新たな経済成長の機会創出とGHG削減の両立をめざす点に特徴があります。日本政府は2023年5月、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)」を施行しました。さらに、2025年2月には「GX2040ビジョン」が閣議決定され、これにあわせてGX推進法および「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源法)」の一部が改正されました。この改正では、成長志向型のカーボンプライシング構想を制度として具体化するための方針が示されており、排出量取引の法定化や資源循環強化を目的とした制度の創設、化石燃料賦課金に関する措置の具体化、さらにはGX分野への財政支援体制の整備が進められています。
GX(グリーントランスフォーメーション)とは、地球温暖化の原因となる温室効果ガス(GHG)排出の抑制を目的に、化石燃料の使用を減らし、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを活用した経済や社会への転換を推進する取り組みです。社会全体の構造を変えるこの活動は、新たな経済成長の機会創出とGHG削減の両立をめざす点に特徴があります。日本政府は2023年5月、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)」を施行しました。さらに、2025年2月には「GX2040ビジョン」が閣議決定され、これにあわせてGX推進法および「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源法)」の一部が改正されました。この改正では、成長志向型のカーボンプライシング構想を制度として具体化するための方針が示されており、排出量取引の法定化や資源循環強化を目的とした制度の創設、化石燃料賦課金に関する措置の具体化、さらにはGX分野への財政支援体制の整備が進められています。
政府は、2050年までにカーボンニュートラルの実現をめざし、2030年度には2013年度比でGHG排出量を46%削減するという国際的な公約を掲げています。2023年度時点では、前年度比で約4%、2013年度比で約23%の削減が確認されていますが、目標達成にはさらなる取り組みが不可欠です。今後5年間で大幅な削減を実現するためには、エネルギー効率の徹底的な改善と再生可能エネルギーのより一層の活用が必要であり、その対策が求められています。
GHG 排出量の削減と循環型経済の構築において、企業の果たす役割は極めて大きなものです。製品やサービスの提供における脱炭素化はもちろんのこと、生産活動や物流、オフィス運営といったあらゆる業務において、GHG 排出の抑制が一層強く求められています。政府はGX推進法のもと、今後10年間で官民あわせて150兆円を超えるGX投資の実現をめざしており、企業にとっても新たな成長機会と位置付けられています。
政府はこうした投資を背景に、「GX2040ビジョン」の中で産業分野ごとの具体的な脱炭素戦略を示しています。例えば、鉄鋼分野では鉄を溶かす際に石炭を利用する「高炉」から、電気を利用する「電炉」への転換が世界の主流になりつつあります。それに加えて日本では、鉄の原料から酸素を取り除く際に水素を利用する独自技術を開発することで、脱炭素化をけん引していく構えです。また、日本のGHG排出量の約16.5%を占める自動車分野では、電気自動車(EV)だけでなく、水素を利用する燃料電池車(FCV)、現在主力のハイブリッド車(HV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)においても、バイオ燃料や合成燃料などの脱化石燃料を活用し、エネルギーの最適な組み合わせを図ることが重要とされています。2035年には、新車販売のすべてを、HVとPHEVを含む電動車とする方針が掲げられており、自動車業界全体での構造転換が加速しています。
建物の脱炭素化を実現するZEB

これまで企業活動の現場では、建物における省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの活用など、脱炭素化へ向けたさまざまな取り組みが継続的に進められてきました。しかし、2050年のカーボンニュートラル実現のためには、さらなるGHG排出量の削減が求められます。こうした中、政府は各種の補助金制度などを通じて建物の脱炭素化を後押ししており、その中でも、より根本的な省エネ対策として注目されているのが「ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル=ゼブ)」です。
ZEBとは、建物で使うエネルギー消費量を実質ゼロにすることをめざした建物のことを言います。具体的には、外部から供給される電力やガスなどの一次エネルギー消費量を、省エネと太陽光発電などの自然エネルギーによる創エネと組み合わせることで、プラスマイナスゼロにすることをめざしています。
新築ビルのように、企画や設計の初期段階からZEB化を前提に進められるケースでは、完全な一次エネルギー消費量ゼロも実現可能ですが、既存の建物では難しいことも少なくありません。ですが、カーボンニュートラル実現のためには新築ビルだけではなく既存の建物も含めた脱炭素化が必要になります。政府はこうした課題に対し、ZEBの導入段階に応じた補助金制度を設けています。新築や大規模改修では、省エネと創エネを組み合わせて一次エネルギーの使用を25%以下に抑える「Nearly ZEB」、省エネのみで50%以上の削減をめざす「ZEB Ready」の基準を、一方、省エネ設備への更新が難しい既存の建物では、段階的なアプローチとして、延床面積が1万㎡以上の公共施設や大規模施設を対象に、「ZEB Oriented」の基準を設けています。具体的には、オフィスや学校、工場などでは40%、ホテルや病院、商業施設などでは30%の省エネ目標を規定し、補助金とともに普及を推進しています。
既存の建物でZEBをめざす場合には、まずは可能な範囲から取り組みを始め、創エネ設備の追加や高効率な最新の省エネ機器への更新を数年単位で計画的に進めることが重要です。さらに、AIやIoT技術などを活用した運転制御によって、エネルギーの無駄を最小限に抑える努力が求められます。
また、こうしたZEBの取り組みは個人の住宅にも広がっています。ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス=ゼッチ)は、家庭においても創エネと省エネを組み合わせ、一次エネルギーの購入量を削減する仕組みです。太陽光パネルを設置する戸建て住宅が増えているだけでなく、年間を通じて温度変化が少ない地下熱を利用した地中熱空調ヒートポンプによる冷暖房システムの導入なども進んでいます。
企業価値を高めるESG経営とGX

近年、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)に配慮した経営を評価し、投資対象とするESG投資という考え方が広がっています。企業が持続可能な成長を遂げるためには、財務的な健全性だけでなく、ESGへの取り組みを継続的に推進していくことが不可欠です。ZEBの推進、脱炭素化の取り組み、そして再生可能エネルギーの積極的な活用など、環境への配慮を経営に組み込んだ企業が、今後投資対象として、企業価値を高めていくとされています。
投資家は、昨今の気候変動や、社会における人権問題などへの関心の高まりを背景に、企業の非財務情報を重視するようになりました。その結果、世界のESG投資市場は急速に拡大し、日本でもその動きが加速しています。さらに、金融庁は2023年3月期から、上場企業に対してサステナビリティ情報の開示を事実上義務付けるなど、政府も情報開示のルール整備を進め、企業と投資家の対話を促しています。今後は、自社の事業活動だけでなく、サプライチェーン全体でのGHG削減や、従業員の働き方、人権への配慮といった側面にも、より一層の注目が集まると考えられます。
政府はこのような企業の努力を後押しするために、さまざまな支援策を講じています。例えば資源エネルギー庁では、工場や事業所単位といった大規模な省エネ対策への支援、製造設備の電化・脱炭素設備への更新やモーター・空調機器の高効率化、エネルギーモニタリングシステムの導入などにかかる費用の一部を補助する制度を設けています。また、環境省でも先述の「建築物等のZEB化・省CO₂化普及加速事業」として補助金を交付しています。これらの補助金制度を上手に活用することで、大幅な省エネによる脱炭素化がより現実的なものとなります。
GXの推進は、単なる環境政策ではなく、日本経済全体の再構築と競争力強化をもたらす重要な成長戦略でもあります。持続可能な未来を実現するためには、私たち一人ひとりも日々の生活の中で環境への配慮を意識し、できることから行動してみてはいかがでしょうか。
関連する記事
メールマガジンで配信いたします。