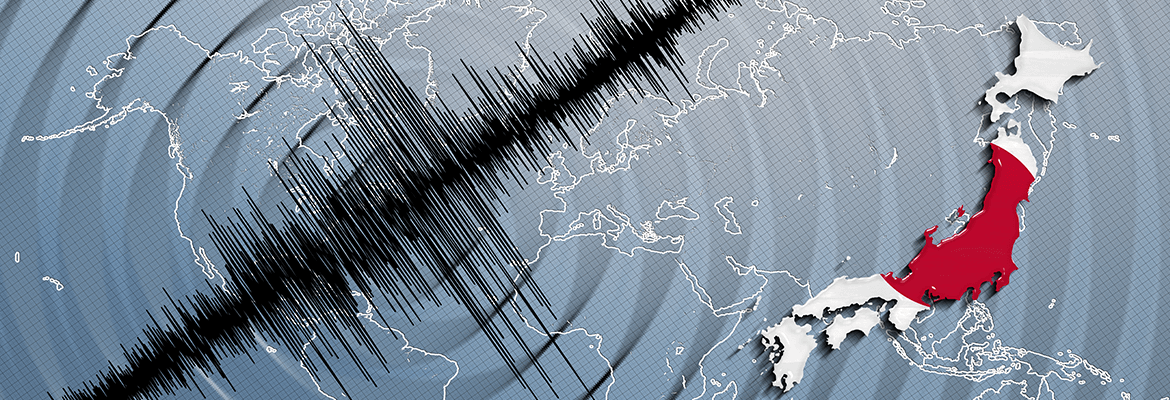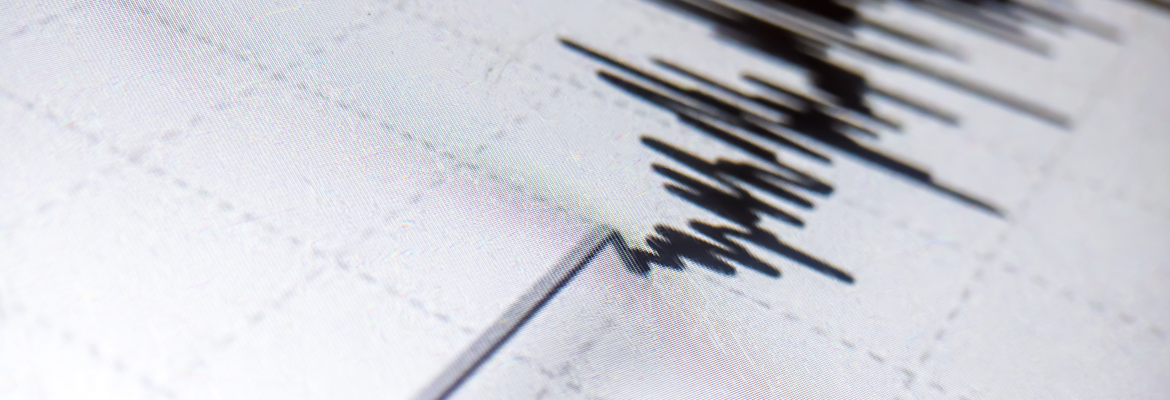日本の象徴である富士山は、300年以上沈黙を続ける活火山です。ひとたび噴火すれば、溶岩流による直接的な被害に加え、降灰が首都圏にまで達することで、通信・電力・交通といった主要なインフラが広い範囲で麻痺する可能性があります。今回はいずれ起こると言われている富士山噴火に対し、想定される被害や影響、そして企業が今から講じるべき対策などについて解説します。
300年の沈黙と迫る噴火の可能性
 日本最高峰、標高3,776mを誇る富士山。四方に裾野を広げた優美な独立峰の姿は、古くから多くの芸術作品の題材となり、今もなお、国内外の観光客を魅了し続けています。その美しい形は、何度も繰り返された噴火によって流れ出た溶岩が、幾層にも積み重なってできた典型的な成層火山の特徴を示しています。
日本最高峰、標高3,776mを誇る富士山。四方に裾野を広げた優美な独立峰の姿は、古くから多くの芸術作品の題材となり、今もなお、国内外の観光客を魅了し続けています。その美しい形は、何度も繰り返された噴火によって流れ出た溶岩が、幾層にも積み重なってできた典型的な成層火山の特徴を示しています。
かつて火山は「活火山」「休火山」「死火山」と分類されていましたが、現在気象庁では、「概ね過去1万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山」を活火山と定義しており、休火山や死火山という区分は廃止されています。これは、火山活動の周期が非常に長く、たとえ数百年噴火していなくても「活動中」と判断する必要があるためです。現在、日本国内には111の活火山が存在しています。
そして、その一つである富士山は、気象庁が指定する「常時観測対象の50火山」に含まれ、防災上、特に警戒が必要とされています。最後の噴火は、江戸時代まで遡り1707年12月16日の「宝永大噴火」です。山頂ではなく現在の宝永山とされる山腹から噴火が始まり、約16日間にわたって断続的に活動が続きました。歴史資料によると、火山灰は偏西風に乗って広がり、遠く離れた江戸市中でも降灰が観測され、当時の人々の生活や農作物、交通に甚大な影響を及ぼしたと記録されています。この噴火の49日前には、南海トラフ全域を震源とする「宝永地震」が発生しており、富士山噴火との関連性が指摘されています。
富士山の噴火周期は、過去の傾向から概ね100年程度とされていますが、1707年以降、300年以上にわたって噴火が起きていないことから、警戒感が高まっています。しかし、政府と山梨県、静岡県、神奈川県および各関係市町村、火山専門家などで構成される「富士山火山防災対策協議会」によると、過去約5600年の間におよそ180回もの噴火が確認されており、富士山が極めて活発な火山であることが分かります。
最近では、東日本大震災直後の2011年3月15日に富士山南部でマグニチュード6.4の地震が発生し、その後もしばらく地震活動が続いていたと報告されています。こうしたことから、自然現象には一定の周期性があり、富士山が今後再び噴火する可能性は十分にあると考えられます。特に、発生確率が高まっている南海トラフ・東南海トラフ地震と連動し、「複合災害」となるリスクも指摘されており、その脅威は非常に深刻です。私たちは、こうした歴史的な背景と最新の科学的知見にしっかりと目を向け、平時から防災意識を高め、具体的な備えを講じていくことが求められています。
富士山噴火がもたらす複合災害

富士山は1707年の宝永大噴火以降、300年以上噴火しておらず、見かけ上は静穏を保っていますが、これは決して安全であることを意味しません。いつ噴火してもおかしくない状況であるという危機感から、政府や関係機関は近年、「富士山ハザードマップ(改定版)検討委員会報告書」や内閣府の「首都圏における広域降灰対策ガイドライン」など、被害想定と防災方針を相次いで改定しています。
富士山の噴火による影響は、周辺地域の直接被害と首都圏を中心とする広範囲の間接被害の二つに分かれます。まず富士山周辺では、火砕流や溶岩流による直接的な被害が最も深刻です。噴火が想定されるのは山頂だけでなく、山梨・静岡両県側の広範囲にわたります。火口に近い地域では、2時間以内に溶岩流が到達する可能性があり、製紙業などが集中する富士市周辺のような比較的距離がある地域へも、7日程度で到達するという試算もあります。さらに積雪期に噴火した場合、急激な融雪により大規模な火山泥流が発生するリスクも高まります。
そして間接的な被害として、重大な影響を及ぼすのが降灰です。宝永大噴火の際には、噴火が16日間続いたことで偏西風に乗った火山灰が関東一円に降り、江戸市中で約2㎝、川崎で約5㎝の降灰が観測されています。もし現代に同規模の降灰があれば、社会インフラ、生活インフラの機能は深刻なレベルで損なわれるでしょう。
たとえば電力分野では、変電所や送電網の碍子(がいし)に灰が付着することで漏電やショートが発生し、大規模な停電を引き起こす恐れがあります。太陽光発電施設も積灰によりで発電能力を失い、代替電力の供給も難しくなります。結果として都市の広域停電や鉄道の運行停止が現実のものとなります。交通・物流面でも、溶岩流や降灰によって高速道路の通行が制限されるほか、わずか0.04〜0.2cm程度の降灰でも空港の滑走路が滑走不能となるため空の便も全面停止することが考えられます。こうしたインフラの麻痺は、地域を超えた全国的な物流機能の停滞にもつながるでしょう。
情報通信分野への影響も深刻です。通信基地局や回線設備に火山灰が積もると機器の故障を招き、広域停電と相まって情報ネットワーク全体が機能不全に陥ります。特に微細な火山灰が情報機器の内部へ侵入すると、運転停止を誘発し、社会機能に極めて深刻な影響を及ぼします。情報ライフラインの遮断は企業活動に甚大なダメージを与える可能性があります。さらに、生活インフラも大きな打撃を受けます。浄水場では火山灰の流入により水処理が停止し、下水道では火山灰が水と混ざり合うことでセメントのように固まり、管の閉塞によって水の逆流や都市型水害を引き起こす恐れがあります。
降灰は、私たちの住環境や健康にも直接的な脅威をもたらします。降灰の後に雨が降ると、灰は水を含んで固まり、その重みが屋根や屋上に加わることで、建物の倒壊リスクが高まります。道路上では視界不良や信号機の故障により混乱が広がり、自動車のエンジンもエアフィルターの目詰まりによって故障するリスクが高まります。さらに、空気中に舞う微粒子状の火山灰は呼吸器系に悪影響を与え、気管支疾患などの健康被害が多発することも予想されます。
企業が講じるべき対応とは
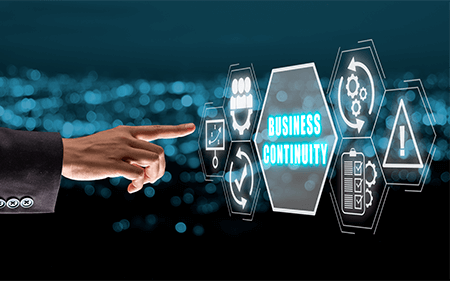
富士山の大規模噴火は、単に自然災害としての被害にとどまらず、首都圏に集中する人口や経済活動が被害を増幅させ、社会システム全体の機能停止を招く危険性もあります。特に、インフラが広範に機能不全に陥れば、生活と経済の両面において被害が極大化する恐れがあります。企業はこうしたリスクに備えるため、噴火に対応する事業継続計画(BCP)の見直しと強化が急務です。多くの企業は、発生確率が高まっている南海トラフ地震や首都圏直下型地震を想定したBCPの整備をすでに進めていますが、富士山噴火はそれらとは性質が異なり、広域に及ぶ降灰被害を想定した対策が必要になります。
この「降灰リスク」への対策をBCPにどう織り込むかが、企業のレジリエンス経営(強靭性のある持続可能な経営)を実現できるかどうかの分かれ道になります。特に工場などの生産拠点が想定被害地域にある企業にとっては、損害のリスクは計り知れません。したがって、短期的な機能移転体制の整備に加え、災害の長期化を見越した拠点の分散化やバックアップ機能の整備も不可欠になります。
また、富士山噴火の影響は日本国内だけにとどまりません。1991年、フィリピンのピナツボ山が噴火した際には、大量の火山灰が成層圏にまで到達し、地球全体の気温が一時的に低下しました。これにより、1993年の日本では冷害による深刻な米不足が発生しました。同様に、江戸時代の1783年には、浅間山などの噴火を契機に天候不順が続き、天明の大飢饉が起きたという記録も残っています。
このように、富士山の噴火が地球規模での気候変動や食料リスクにつながる可能性も否定できません。だからこそ、企業や自治体は富士山噴火を「他人事」とせず、実際に起こり得る「現実的なリスク」として向き合う必要があります。政府や関係自治体では各種ハザードマップや被害想定資料を公開しており、それらを積極的に活用し、具体的な対策に落とし込むことが求められます。
特に企業には、平時から災害リスクを考慮した事業拠点・機能の分散やサプライチェーンの多重化などを進める責任があります。それは災害時における損失を最小限にとどめるだけでなく、社会全体の持続的な経済活動を守るという観点からも重要な取り組みです。富士山噴火という潜在的なリスクに真摯に向き合い、企業・行政・個人が一体となって備えを固めることが、これからの時代における持続可能な社会づくりの第一歩となるのではないでしょうか。
関連する記事
メールマガジンで配信いたします。