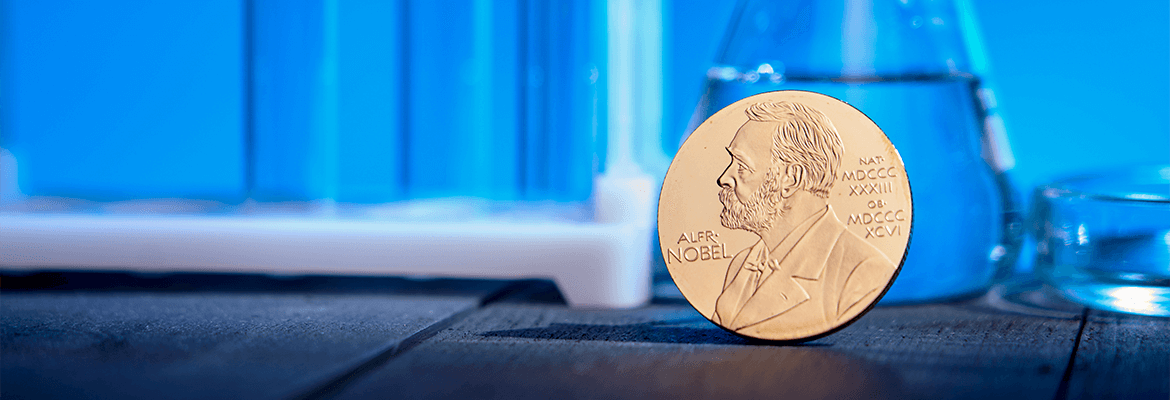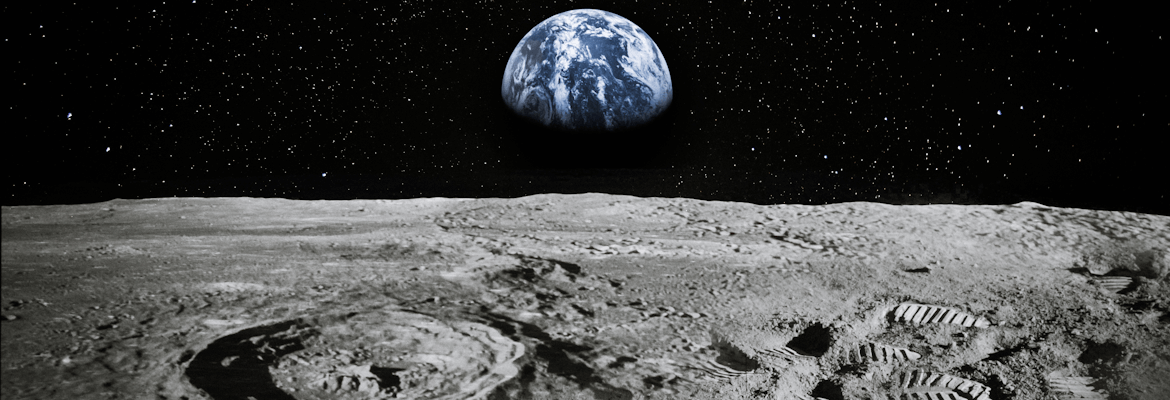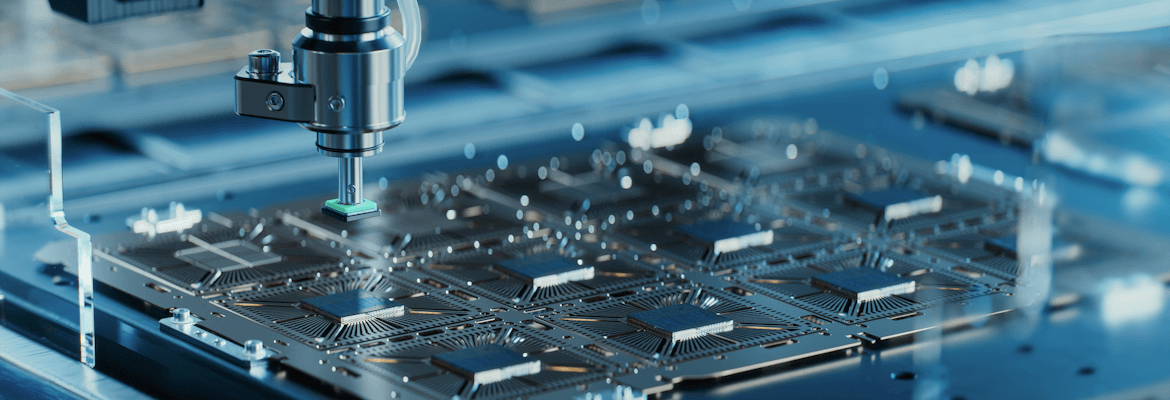毎年10月が近づくと、メディアが大きく取り上げるノーベル賞受賞者の発表。2025年は生理学・医学賞と化学賞で、日本人研究者の2名受賞が決定しました。今回は、ノーベル賞の仕組みや歴史、日本人受賞者の歩み、そして基礎研究がどのように社会や未来の技術を支えているかについて解説します。
毎年注目を集める「ノーベル賞」の歴史と概要
 ノーベル賞は、スウェーデンの発明家アルフレッド・ノーベル(1833~1896年)の遺言をもとに創設された、世界で最も権威のある学術賞の一つです。ノーベルはダイナマイトの発明により巨額の富を築き、「人類に大きく貢献した人々に財産を使ってほしい」と遺言に記しました。その意思に基づいて物理学、化学、生理学・医学、文学、平和の5賞が創設され、1901年から授与されています。この5賞とは別に経済学賞が存在しますが、これはノーベルの遺言によるものではなく、スウェーデン国立銀行が創立300周年記念として1968年に創設した賞です。翌1969年から授与が始まり、正式にはノーベル賞と区別されることもありますが、現在では一般的に「ノーベル経済学賞」と呼ばれています。
ノーベル賞は、スウェーデンの発明家アルフレッド・ノーベル(1833~1896年)の遺言をもとに創設された、世界で最も権威のある学術賞の一つです。ノーベルはダイナマイトの発明により巨額の富を築き、「人類に大きく貢献した人々に財産を使ってほしい」と遺言に記しました。その意思に基づいて物理学、化学、生理学・医学、文学、平和の5賞が創設され、1901年から授与されています。この5賞とは別に経済学賞が存在しますが、これはノーベルの遺言によるものではなく、スウェーデン国立銀行が創立300周年記念として1968年に創設した賞です。翌1969年から授与が始まり、正式にはノーベル賞と区別されることもありますが、現在では一般的に「ノーベル経済学賞」と呼ばれています。
ノーベル賞は当初、故人の業績も対象としていましたが、現在は受賞発表時に存命している人のみが対象となっています。受賞者の発表は毎年10月初旬に行われ、最初に生理学・医学賞、翌日に物理学賞、続いて化学賞といった自然科学分野にあたる3賞、その後、文学賞と平和賞、最後に経済学賞という流れで発表されています。受賞者は大学や研究機関の研究者が多いものの、企業で研究開発に取り組む人が選ばれることもあります。選考を行う機関は賞によって異なり、平和賞のみノルウェーのオスロにあるノルウェー・ノーベル委員会が担当しています。それ以外の賞はすべてスウェーデン国内の機関が担っており、物理学賞、化学賞、経済学賞はスウェーデン王立科学アカデミー、生理学・医学賞はカロリンスカ研究所、文学賞はスウェーデンアカデミーが選考を行います。
授賞式は12月初旬に開催されます。平和賞はノルウェーのオスロ市庁舎で行われ、それ以外の賞は、スウェーデンのストックホルム・コンサートホールが舞台です。式典の後には盛大な晩餐会や記念講演が続き、受賞者はその後、各地で講演や交流活動を行うのが通例です。受賞者には賞状とメダル、そして多額の賞金が授与されます。この賞金はノーベルの遺産を管理するノーベル財団の運用益から支払われ、その潤沢な原資が賞の権威を支えています。たとえば、2024年の賞金は1,100万クローナ(約1億7,800万円)でした。この資金は、受賞者がその後の研究をさらに推進していく後押しとなります。共同受賞の場合は賞金を受賞者で分け合いますが、メダルと名誉は何物にも代えがたい「人類への貢献の証し」として輝き続けていきます。
日本人とノーベル賞

世界中の研究者にとって最高の栄誉であるノーベル賞に日本人が初めてその名を刻んだのは、戦後間もない1949年、中間子の存在を理論的に予言し、物理学賞を受賞した湯川秀樹氏です。敗戦により国全体が落ち込み、未来への希望を失いかけていた当時の日本にとってこの受賞は、日本が世界の科学研究の舞台へ戻ってきたという象徴的な出来事となり、多くの国民に自信と希望を与えました。
その後、日本人研究者は自然科学の分野で成果を上げ続け、物理学賞は湯川氏を含めてこれまで12人、化学賞は1981年の福井謙一氏を皮切りに、今回の北川進氏を含め9人が受賞しています。特に2002年、京都の分析機器メーカーに勤務するエンジニア、田中耕一氏が化学賞を受賞した際は、「企業に勤めるサラリーマンがノーベル賞」というインパクトが大きな話題となりました。この受賞は、基礎研究が大学や公的研究機関だけではなく、企業の現場にも存在することを広く示した出来事でした。
生理学・医学賞については、1987年の利根川進氏以来、しばらく日本人受賞者が出ない時期が続きましたが、2012年にiPS細胞を作製する技術の確立で山中伸弥氏が受賞して以降、受賞者が増加しています。そして今回の坂口志文氏(生理学・医学賞)、北川氏(化学賞)の受賞決定により、日本人の自然科学3賞の受賞者は外国籍取得者を含め合計27人となりました。これは、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスに次ぐ世界第5位の受賞者数です。さらに、2000年以降に限ると21人が受賞しており、そのペースは、ドイツやフランスを上回る水準で、日本の基礎科学研究の高さを世界に示しています。
なお自然科学3賞以外では、文学賞において1968年に川端康成氏、1994年に大江健三郎氏が受賞しています。平和賞では、1974年に佐藤栄作元首相が受賞し、2024年には日本原水爆被害者団体協議会が団体として受賞しています。
ノーベル賞では、候補者名は選考の公平性と独立性を保つため原則50年間非公開です。しかし、このルールが解除され公開された過去の資料によると、日本における細菌学の先駆者である北里柴三郎氏や黄熱病研究で知られる野口英世氏が、かつて生理学・医学賞の有力候補者だったことも明らかになっています。毎年10月が近づくと、メディアでは「今年の受賞者は誰か?」と期待が高まりますが、正式な候補者がわかるのは、受賞から半世紀後ということになります。
ノーベル賞が世界的な権威を持ち続けている理由は、単に賞金の大きさや歴史の長さによるのではありません。厳格な選考プロセスと、「人類への最大の貢献」という高潔な理念のもと、過去から現在まで受賞者一人ひとりの業績が積み重ねられてきた結果として、その価値と信頼が築かれているからです。この権威こそが、世界中の研究者の情熱と挑戦を支え、地道な基礎研究を続ける原動力となっているのです。
科学の発展と経済成長を支える基礎研究の役割

物理学、化学、生理学・医学の自然科学3賞は、理論や実験による基礎研究の業績が評価されます。そして、地道な研究活動を通じて得られたこれらの知見は国際的な論文として発表され、多くの研究者が引用することでその価値が確かめられていきます。この積み重ねこそが、後に続く応用研究や技術開発の礎となり、一見すると日常生活からは遠く感じられますが、その成果が私たちの生活を大きく変えていくのです。
その象徴的な例が、1956年に物理学賞を受賞したウィリアム・ショックレー、ジョン・バーディーン、ウォルター・ブラッテンの3人による「トランジスタ」の発明です。トランジスタは、それまでの真空管に代わり電子機器の小型化と省電力化を可能にし、やがてLSI(大規模集積回路)へと発展しました。この小さな半導体素子が、スマートフォン、パソコン、サーバーなど、現代のデジタル社会を支えるあらゆる技術の原点となったのです。もしこの基礎研究がなければ、現在のデジタル社会は存在しなかったと言っても過言ではありません。
近年の例では、2014年に青色発光ダイオード(LED)の発明で赤崎勇氏、天野浩氏、中村修二氏(米国籍)が物理学賞を受賞しています。青色LEDの実現により白色LEDが誕生し、世界中で省エネルギーな照明として普及しました。この成果は、地球規模のエネルギー消費削減と環境問題への貢献につながっています。
そして、今回の日本人受賞決定者の業績も、未来の社会課題解決に大きく貢献することが期待されています。化学賞の受賞が決定した北川進氏らの「金属有機構造体(MOF)」は、細かな孔が無数に空いた特殊な構造を持ち、CO₂を効率よく吸着して閉じ込めることができます。これはCO₂削減や資源化といった地球温暖化対策に新しい可能性をもたらします。また、生理学・医学賞の共同受賞が決定した坂口志文氏が発見した「制御性T細胞(Treg)」は、免疫が過剰に働くことを抑えるメカニズムを解明したもので、難病である自己免疫疾患の治療やがん免疫療法の進展に大きく寄与する可能性を秘めています。
研究者にとってノーベル賞受賞は、研究の終着点ではありません。むしろ、基礎研究の重要性を社会全体に問いかける機会であり、その成果が新しい産業や医療、技術の創出につながる入口でもあります。長い時間をかけて進められる基礎研究こそが、病気を治す治療法を生み出し、私たちの生活を豊かにし、経済成長を支える源泉なのです。
日本が科学技術で世界に貢献し続けるには、研究者が自由な発想で基礎研究に取り組める環境を整えることが不可欠です。行政は研究に必要な予算や支援を継続的に確保し、企業は基礎研究の成果を応用研究や事業化につなげる役割を担う。こうした連携こそが、日本の科学力をさらに高め、人類社会への貢献につながっていくのではないでしょうか。
関連する記事
メールマガジンで配信いたします。