2025年4月13日、大阪・関西万博が大阪府夢洲(ゆめしま)で約半年間にわたり開催されます。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げた同万博は、会期中の来場者数約2,820万人、経済波及効果約2.9兆円と試算されています。近年、地球温暖化をはじめ社会が抱える課題が複雑化するなか、世界の英知を集結させ、これら課題の解決策を見出す場として注目が集まっています。今回は、そもそも万博とはなにか、そして万博の歴史や目的などについて解説します。
そもそも万博とは?
 万博(万国博覧会)とは、国際博覧会条約に基づき正式に博覧会国際事務局(BIE:Bureau International des Expositions)に登録・認定された博覧会を示し、正式名称は国際博覧会です。国際博覧会条約では、国際博覧会を「2以上の国が参加したもの。公衆の教育を主たる目的とする催しであって、文明の必要とするものに応ずるために人類が利用することのできる手段または人類の1もしくは2以上の部門において達成された進歩もしくはそれらの部門における将来の展望を示すもの」と定義しています。
万博(万国博覧会)とは、国際博覧会条約に基づき正式に博覧会国際事務局(BIE:Bureau International des Expositions)に登録・認定された博覧会を示し、正式名称は国際博覧会です。国際博覧会条約では、国際博覧会を「2以上の国が参加したもの。公衆の教育を主たる目的とする催しであって、文明の必要とするものに応ずるために人類が利用することのできる手段または人類の1もしくは2以上の部門において達成された進歩もしくはそれらの部門における将来の展望を示すもの」と定義しています。
世界各国が自国の文化や伝統、画期的な技術などを紹介し国際交流と社会の発展、それらによる未来に向けた展望の創出を目的に開催されます。
世界初の国際博覧会は、1851年にロンドンで開催された「第1回ロンドン万博博覧会」で、25か国が参加しました。メイン会場となったハイドパークに鉄とガラスでできた「クリスタルパレス(水晶宮)」を建設、産業革命の成果を世界に披露し604万人の入場者を集めました。1851年当時のイギリスはビクトリア王朝時代で、まさに「大英帝国」が世界の覇権を握っていた時代です。一方、日本は江戸時代の終焉前夜である幕末でした。2年後の1853年にはペリー艦隊が浦賀に来航し、まさに動乱時代の幕が開くことになります。1862年には「第2回ロンドン万国博覧会」が開催され、日本の文久遣欧使節団が視察しました。この時の模様を福沢諭吉が著書「西洋事情」に書き残しています。
日本が初めて参加した国際博覧会は1867年に開催された「第2回パリ万国博覧会」です。同博覧会には幕府に加えて薩摩藩、鍋島藩が、それぞれ薩摩焼や伊万里焼など陶芸作品を出展し注目を集めました。長く鎖国状態にあり、オランダなど限られた国にしか門戸を開いてこなかったことで、日本の出展品は注目を集め、ジャポニズムが広がる契機となりました。同博覧会は、ロンドン万博に対抗心を燃やすナポレオン三世が1863年に開催を命じたことで実現し、娯楽施設を配した会場設計などがその後の国際博覧会に影響を与えたと言われています。以降パリでは、1878年に第3回、1889年に第4回、19世紀最後となる1900年には第5回を開催しています。フランス革命から100年の年に開催された1889年の「第4回パリ万国博覧会」ではエッフェル塔が建設されたほか、エディソンの発明による白熱電灯で会場が照らし出され、万博史上初の夜間開場が実現しました。また、1900年に開催された「第5回パリ万国博覧会」においては、動く歩道や地下鉄が初めて一般に公開されました。当時の人々にとっては驚異的な技術革新で、多くの観客が体験しようと殺到したと伝えられています。
国際博覧会はオリンピックのように4年に1回の開催と決められているわけではなく、毎年開催されたケースや同じ年に複数の国で開催されていたケースもあります。第一次世界大戦や第二次世界大戦などによって休止期間はあったものの、各国で頻繁に開催されています。
なお、現在の日本政府として初めて参加した国際博覧会は、1873年に開催された「ウィーン万国博覧会」です。展示会場にしつらえた日本庭園は評判となり、好評を博したと言われています。
日本が開催した国際博覧会の歴史
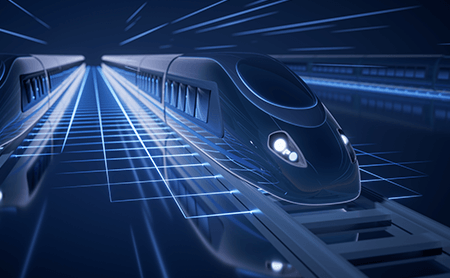
日本が開催した初めての国際博覧会は55年前、1970年に大阪府千里丘陵で開催した「日本万国博覧会」です。会期は3月15日から9月13日まで183日間、海外77か国・地域に加えアメリカ3州と2都市、カナダ3州などのほか、国内32団体・企業が参加しました。同博覧会は統一テーマを「人類の進歩と調和」とし、サブ・テーマとして「より豊かな生命の充実を」「よりみのり多い自然の利用を」「より好ましい生活の設計を」「より深い相互理解を」の4つが設定されました。アメリカ館に展示された「月の石」や、国内電機メーカーの「人間洗濯機」、旧ソ連館には宇宙船「ソユーズ」の実物が展示され、それらが人気を集め、半年間の会期中にのべ6,400万人超が来場しました。2010年に開催された「上海国際博覧会」に抜かれるまで過去最多を記録するとともに、国際博覧会史上初めて黒字となった万博とも言われています。同博覧会の会場となった千里丘陵は、万博記念公園として現在も岡本太郎氏デザインの「太陽の塔」が残されています。
続いて1975年には「海-その望ましい未来」をテーマとした「沖縄国際海洋博覧会」を沖縄県国頭郡本部町で開催。同博覧会は、沖縄の日本復帰を記念し、全国民をあげてこれを祝うことを目的として開催されました。また「海洋」をテーマにした世界で初めての博覧会であり、36か国・3国際機関が参加し約349万人が来場しました。1985年には「人間・居住・環境と科学技術」をテーマとした「国際科学技術博覧会」を茨城県筑波研究学園都市で開催。48か国・37国際機関が参加し、リニアモーターカーのHSST(High Speed Surface Transport)が注目を浴び、約2,033万人が来場しました。
さらに、1990年には「自然と人間との共生」をテーマとした「国際花と緑の博覧会」を大阪市鶴見緑地で開催。21世紀へ向けて、花と緑と人間生活の共生により、潤いのある豊かな社会の創造をめざし、アジアで初めて開催された国際園芸博覧会です。83か国・37国際機関、18団体が参加し、「国際科学技術博覧会」を上回る約2,312万人が来場しました。直近では、2005年に「自然の叡智」をテーマとした「2005年日本国際博覧会」通称「愛・地球博」を愛知県瀬戸市南東部,豊田市,長久手町で開催。121か国・4国際機関が参加したほか、一般参加として企業や行政に加えて、市民やNPO/NGOの参加も認められ、約2,200万人が来場しました。
そして、2025年に大阪府夢洲で開催する「2025年日本国際博覧会」のほか、2027年には神奈川県横浜市で「幸せを創る明日の風景」をテーマとした「2027年国際園芸博覧会」の開催が予定されています。
国際博覧会に今求められるものとは
 近年、地球温暖化や資源の枯渇、AI技術の急速な発展など、社会が抱える課題は複雑になっています。その中で国際博覧会は、世界の英知を集結させ、これらの課題に対する解決策を見出す場としてこれまで以上に重要度を増しています。また、世界が等しく経験した新型コロナウイルス感染症の影響により、「いのち」を取り巻く環境やさまざまな社会制度の再構築、価値観や生活様式の変化など、新たな課題に直面することになりました。こうした状況だからこそ、世界の英知を結集し、速やかに解決へと導くことが求められています。
近年、地球温暖化や資源の枯渇、AI技術の急速な発展など、社会が抱える課題は複雑になっています。その中で国際博覧会は、世界の英知を集結させ、これらの課題に対する解決策を見出す場としてこれまで以上に重要度を増しています。また、世界が等しく経験した新型コロナウイルス感染症の影響により、「いのち」を取り巻く環境やさまざまな社会制度の再構築、価値観や生活様式の変化など、新たな課題に直面することになりました。こうした状況だからこそ、世界の英知を結集し、速やかに解決へと導くことが求められています。
2025年4月開幕を目前に控えた「2025年日本国際博覧会」(略称「大阪・関西万博」)は、158か国・9国際機関が参加とこれまでにない大きな規模での開催が予定されています。テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。同テーマには、一人ひとりが自らの望む生き方を考え、それぞれの可能性を最大限発揮できるようにするとともに、こうした生き方を支える持続可能な社会を共創していくという思いが込められています。同博覧会は、格差や対立の拡大といった新たな社会課題、AI、バイオテクノロジーなどの科学技術の発展といったさまざまな変化に直面する昨今において、参加者一人ひとりに対し、自らにとって「幸福な生き方とは何か」を正面から問う初めての国際博覧会であり、2015年に国連本部で採択された、「持続可能な開発目標(SDGs)」が達成される社会をめざし開催されます。
さらに、同博覧会を通して日本の魅力を広め、より付加価値の高い観光立国の実現をめざすきっかけとすること、そして経済、社会、文化などあらゆる面において、大阪・関西のみならず、日本全体にとってさらなる飛躍の契機となることも期待されています。大阪・関西万博が、これまでの国際博覧会の歴史を受け継ぎ、さらなる飛躍を遂げることを願いつつ、私たちも自分にとって「幸福な生き方とは何か」を今一度考えてみてはいかがでしょうか。
関連する記事
メールマガジンで配信いたします。

























