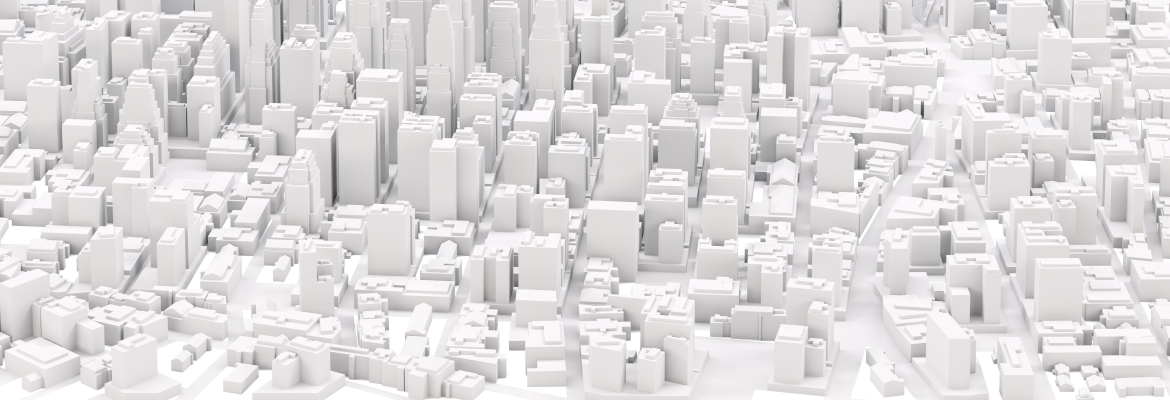前回は、日本政府が「データ利活用型スマートシティ」と呼ぶ、データを活用した街づくりの動向について紹介しました。そうした街づくりにおいて重要になるのが「都市OS」と呼ばれるデータプラットフォームです。都市OSは、地域にダイナミックなデータの循環をもたらし、街づくりやビジネスにイノベーションをもたらすと考えられています。今回は、都市OSの概要や動向をお届けします。
都市の競争力を高めるのはデータの連携
 都市OSとは、都市に存在する膨大なデータを蓄積・分析するとともに、他の自治体や企業、研究機関などと連携するためのプラットフォームのことです。とりわけ重要になるのが、データを連携するという部分。その理由は、都市OSをコンピュータのOS(オペレーティングシステム)に置き換えて考えてみるとわかりやすくなります。
都市OSとは、都市に存在する膨大なデータを蓄積・分析するとともに、他の自治体や企業、研究機関などと連携するためのプラットフォームのことです。とりわけ重要になるのが、データを連携するという部分。その理由は、都市OSをコンピュータのOS(オペレーティングシステム)に置き換えて考えてみるとわかりやすくなります。
OSが登場する前のコンピュータは、用途が限られた専用機でした。そのため、コンピュータが異なると同じプログラムが利用できませんでした。しかし、コンピュータにOSが搭載されるようになると状況が変わります。OSが同じであれば共通のプログラムを利用できるようになり、コンピュータの利便性は大幅に向上しました。昔からコンピュータを使ってきた人なら、Windows®の登場で、異なる会社から発売されたコンピュータで同じオフィスソフトが利用できるようになったことを記憶しているかもしれません。
従来の都市は、OSを欠いたコンピュータのようなものでした。都市それぞれで欲しい情報を得るためだけにシステムの構築が進められ、取り組みごとに独自のシステムが採用されてきました。その結果、ある都市が便利なサービスを開発しても、他の都市に横展開しづらい、あるいは有用なデータを複数の分野にまたがって共有するのが難しかったのです。
こうした状況を打破するために、ICTシステムやデータなどの規格を統一した都市OSにより、都市間や都市と企業間などでデータやサービスの連携や再利用を可能にしようというのが今日のスマートシティの流れなのです。
また、都市OSの開発に関わることは、都市の抱えるデータにアクセスでき、エネルギーや交通、医療、金融、通信、教育などの分野に参入する機会にもつながるため、企業の参入も相次いでいます。特にプラットフォーマーと呼ばれるような巨大ICT企業は、各国の事業に参画してプロジェクトを先導するなど、熾烈な開発競争を繰り広げています。
日本版都市OSの3要件とは
 日本では、2012年ごろからスマートシティの実証事業が各地で行われてきました。しかし、取り組みごとに規格がバラバラだったため、優れた事例やサービスが現れても横展開につなげることができませんでした。
日本では、2012年ごろからスマートシティの実証事業が各地で行われてきました。しかし、取り組みごとに規格がバラバラだったため、優れた事例やサービスが現れても横展開につなげることができませんでした。
こうした欠点を解消するため、2020年3月に政府は都市OSの要件をまとめた「スマートシティリファレンスアーキテクチャ」を発表しました。そこで挙げられたのが、「相互運用(つながる)」「データ流通(ながれる)」「拡張容易(つづけられる)」という要件です。
「相互運用」で必要なのは、標準化団体が定めた共通的な機能や標準的なインターフェースを採用し、異なる都市や企業などと連携を図ることです。また、取り組みの中で生まれたサービスや成果を公開し、外部からのアクセスを可能にする仕組みも求められます。
「データ流通」には、さまざまなデータを分野や組織の壁を越えて連携させる仕組みが欠かせません。都市OSでは、地域内にある地理空間データやパーソナルデータ、統計データなど多種多様なデータが蓄積されます。また、地域外のデータも扱うことがあるでしょう。そのため、異なる種類のデータを仲介する仕組みが必要になります。
従来の独自規格を採用したICTシステムは、機能拡張に多大なコストや労力を要していました。「拡張容易」を満たすようになると、地域のニーズに応じて提供するサービスを柔軟に変更することができます。
日本版都市OSでは、この3つの要件を備えたプラットフォームを目指しています。
近づく都市OSの実装
 日本版都市OSはまだ実証事業が行われている段階ですが、世界ではすでに実装がはじまっているものもあります。
日本版都市OSはまだ実証事業が行われている段階ですが、世界ではすでに実装がはじまっているものもあります。
先進的な都市OSの1つに、欧州の官民連携プロジェクトで開発された「FIWARE(ファイウェア)」があります。FIWAREは、7つカテゴリー、約40種のモジュール群で構成されるソフトウェアの集合体です。その中から、用途に応じてソフトウェアを組み合わせ、都市OSを構築することができます。
FIWAREのソフトウェアはライセンス・ロイヤリティフリーとなっており、低コストで利用できるのも魅力です。そのせいか、100以上の都市で導入されています。日本でも、香川県のある都市がFIWAREを活用して都市OSを構築しようとしています。
欧州の中でも電子国家と呼ばれるエストニアは、独自の「X-Road」と呼ばれるデータ連携基盤技術を開発しています。これにより、エストニアでは、ほぼすべての行政手続がオンラインで行える環境が整っているのです。なお、X-Roadも、2019年6月に千葉県のある都市がシステム開発に導入することを発表しています。
このように各国の影響も受けながら、日本版都市OSの開発は進んでいます。日本では、2019年8月に、「スマートシティ官民連携プラットフォーム」が設立されました。これには、内閣府、総務省、経済産業省、国土交通省が立ち上げに関わっており、縦割りの状態では難しい都市の分野横断的な課題解決に取り組もうという意欲が見えます。
幸い日本には、スマートシティの取り組みがかなり進んでいる分野もあります。例えばエネルギーの分野では、大型のビルや工場などに「BAS(Building Automation System)」や「BEMS(Building Energy Management System)」と呼ばれる総合管理システムが導入され、エネルギー消費の見える化や制御が行われてきました。さらに、地域のエネルギー管理を行う「CEMS(Community Energy Management System)」というシステムの運用もはじまっています。こうした既存の取り組みや技術と都市OSが結びつくことで、データ利活用型スマートシティの実現も大きく前進することでしょう。
すでに日本では、13の地域でデータ利活用型スマートシティの実証事業が行われており、そうした取り組みの中から、日本版都市OSとなるような成果も登場することでしょう。エストニアの例からも分かるように都市OSの実装は、都市のDX(デジタルトランスフォーメーション)を一気に進展させます。都市OSが都市での生活や仕事をどのように変えていくのか、今後も目が離せません。
関連する記事
関連する商品・サービス
メールマガジンで配信いたします。
メールマガジンで配信いたします。