横田真一プロは、ほんの一握りと言われるツアープレーヤーの顔と、医学修士の顔を持つ異色のプロゴルファーです。また最近ではYouTuberとしても人気を集め、ゴルフ人気の向上に尽力するなど活躍の場を広げています。今回は、ゴルフとの出合いからプロゴルファーとしてデビューし、ツアー優勝を挙げるまでの道のりを振り返っていただきながら当時の思いをお話いただきました。
ゴルフに打ち込む学生時代
 ――横田プロがゴルフを始めるきっかけはどこにあったのでしょうか
――横田プロがゴルフを始めるきっかけはどこにあったのでしょうか
ゴルフ好きの父の影響でゴルフを始めました。父は毎週末練習場に通っており、私が小学1年生になると時折練習場に連れていってくれるようになりました。小学3年生の時にジュニア用のクラブを買ってもらい、そこから本格的に始めました。当時の私は、東京都八王子市高尾町に住んでおり、練習場に行く以外は、高尾山の渓流で釣りをするか近所の空き地でゴルフをして遊んでいました。空き地でのゴルフは、私に影響された友人も一緒になって遊んでいたので、友人の多くが卒業文集に「趣味はゴルフ」と書いていましたね。
中学校に入学する春に、父の転勤で茨城県水戸市に引っ越し、住んでいた団地の中にゴルフ練習場があったため毎日通うようになりました。中学校ではなにかしらの部活に所属する必要があったのでテニス部に所属し、夕方部活の練習が終わると、自宅で夕食を済ませ、それから練習場に向かい夜10時くらいまで球を打つことが日課でした。中学2年生の春からジュニアの大会に出場するようになり、そこで好成績を挙げたこともあり、当時ゴルフの名門校と言われていた水城高等学校へ進みました。
そこで、今でも私が日本一の監督だと思う石井貢監督に出会いました。石井監督は、ゴルフ練習に打ち込むことができる環境をしっかり作ってくださる素晴らしい指導者でした。「毎日どれだけコツコツ練習するかが大事」というのが石井監督の口癖で、6時半~7時半までの朝練で150球ほど打ち、放課後は2~3時間で300球ほど打つという、合計450~500球の練習を毎日行っていました。当時そこまで練習する高校のゴルフ部は日本にはなかったと思います。「日本一の練習量だから一緒にやろう!」と私が誘ったのが片山晋呉プロと宮本勝昌プロ。2人とも高校卒業後は日本大学ゴルフ部に進み、その後の活躍は目を見張るものがありましたね。
――日本大学に進んだ後輩2人に対し、横田プロは専修大学に進みました
もちろんプロゴルファーになりたい気持ちはありましたが、それほど簡単なものではないことを理解していましたので、しっかりと大学を卒業し、プロになれなければ就職しようと考えていました。父も会社員でしたし、母が常々「面倒を見るのは大学まで」と言っていたので、それをかなり意識していました。専修大学の生田キャンパスは「川崎国際生田緑地ゴルフ場」に隣接していたこともあり、当時営業時間外は自由に使わせてもらえました。7時くらいまでの朝練を経て大学へ通い、午後3時くらいからコースで目土を行いながらラウンドさせてもらうという生活を送っていました。
プロテストに一発合格!ルーキーイヤーでシード権獲得
 ――大学卒業後プロになるまでの道のりを振り返るといかがですか
――大学卒業後プロになるまでの道のりを振り返るといかがですか
大学卒業後は静岡県沼津市にある「愛鷹シックスハンドレッドクラブ」に研修生として入社しました。当時、プロゴルファーをめざす人が10,000人近く居て、プロと言われる人が2,000人、その中でも第一線で活躍できているのがわずか60人ほどでした。プロになれれば、ゴルフ場に高給で雇ってもらえるので、ツアーには出られないとしても、とにかくまずプロテストに合格して「プロゴルファー」という称号が欲しいと考えていましたね。
そんな思いで受けたプロテストは、それはもう尋常じゃないほど緊張しました。私が受験した頃はプレ予選の後、1次プロテストから6次プロテストまでありました。3次プロテストに合格できれば、日本プロゴルフ協会にプロとして認定されます。4次プロテストから6次プロテストは翌年度のツアー出場資格を争う現在のQT(クォリファイングトーナメント)と言われるもので、私は一回で合格できたうえに6次プロテストでも奇跡的に上位に入れたことから、翌年度のツアーに参加することができました。
――プロデビューの年にシード権を獲得され、1997年にはツアー初優勝を経験、2005年度からJGTO(日本ゴルフツアー機構)選手会長を務められるなど順風満帆なプロゴルファー人生を歩んでいらっしゃいました
2005年度はJGTO選手会長として飛び回りつつも、過去最高の賞金ランク14位を記録しました。確かにここまでは順風満帆だったかもしれませんが、その後2006年にシード権を失ってしまいました。その原因として、選手会長の活動が多忙だったためと言われたりもしましたが、事実は違います。その時期ちょうどクラブの契約メーカーが変わり、新たなメーカーの職人さんたちと、とことん話し合いながら、自分にとってしっくりくる「顔」を持ったクラブに仕上げる努力を続けていました。ところが、完成までに予想以上の時間を費やしてしまい、結果的にその間の成績が上がらずにシード権を失ってしまったのです。そうして2007年度はセカンドツアーであるチャレンジトーナメントに参加することになりました。
チャレンジトーナメント2戦目、エバーライフチャレンジの練習ラウンド中に、職人さんたちが苦心し完成したクラブがゴルフ場に届きました。ようやくしっくりくるクラブを手にし、その大会でまず優勝。次戦の望月東急JGTOチャレンジで2勝目を挙げ、本来の自分のゴルフを取り戻し、2008年度には無事レギュラーツアーのシード権を獲得できました。
自律神経をコントロールし2度目のツアー優勝を果たす
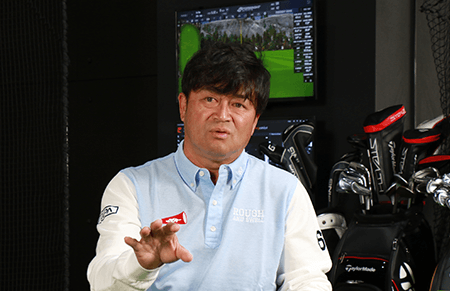 ――レギュラーツアーに復帰して2010年のキヤノンオープンでは見事優勝されましたね
――レギュラーツアーに復帰して2010年のキヤノンオープンでは見事優勝されましたね
キヤノンオープンの3日目が終わり、トーナメントリーダーに私と谷原秀人プロ、そして飛ぶ鳥を落す勢いだった石川遼プロが並んでいました。3日目ラウンド後の記者会見の場で「横田さん、明日勝つことになると13年ぶりの優勝ということになりますね」と聞かれ「いやいや、たぶん明日は85~86くらい叩いちゃいますよ」と返したところ会場がどっと沸きました。プロといってもトップの中のトップにいる人は別として、一生に何度も優勝争いができるわけではありません。トップ争いが久しぶり、且つほかの2人には勢いがあるので、正直勝てるかどうか不安でした。ですが、会見場がどっと沸いたことで私の心がスーっと楽になり、不安も消え、翌日悲願だったツアー2勝目を果たしたのです。「若い時の苦労は買ってでもせよ」とよく言われますが、最初に悔しい思いをしなかった分、ゴルフに対する謙虚さやひたむきさが足りなかったかなと今振り返ると後悔しています。
――13年ぶりの優勝ですが、なぜ優勝できたとお考えですか
医学修士をめざしたきっかけでもある、順天堂大学医学部の小林弘幸先生の助言が大きくかかわっています。2010年のある日、小林弘幸先生に「横田さん、自律神経をコントロールできたらまた優勝できますよ」と言われ、自律神経のコントロールについて教えていただきました。心身のコンディションを良い状態に保つためには「血流」が重要であり、血管を収縮させる交感神経(興奮)と血管を弛緩させる副交感神経(リラックス)が高い水準でバランスした時、程よい血流となり良いパフォーマンスを発揮できるのだそうです。血流が悪いと筋肉が思うように収縮せず体を動かすことが難しくなりますし、脳の働きが低下し思考力や集中力、判断力が鈍くなりますから。先生によれば、現代社会はほとんどの人が交感神経優位のストレス社会であり、だからこそ超一流と言われる人たちに必要なのは、副交感神経が優位な状態とのこと。そう解説いただき納得した私は、試合で意気込みすぎていたかもしれないと反省し、バランスに注意しつつ「副交感神経優位で行こう」と意識するようになりました。そして半年くらい試行錯誤する中でキヤノンオープン優勝に至ったのです。
【後編】では、医学修士の立場から最大のパフォーマンスを発揮する方法などについて解説いただきます。後編は「2025年1月29日(水)」の公開予定となっております。素敵な読者プレゼントもありますのでお楽しみに!
関連する記事
メールマガジンで配信いたします。

























