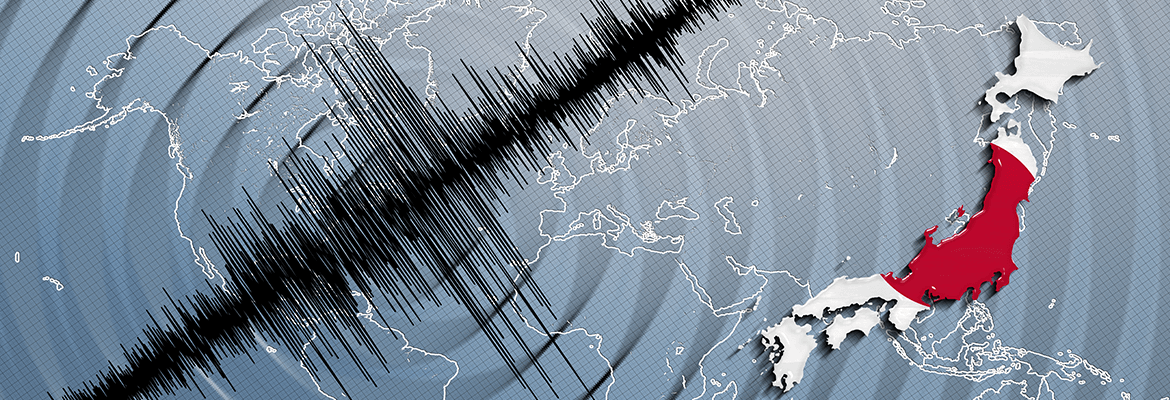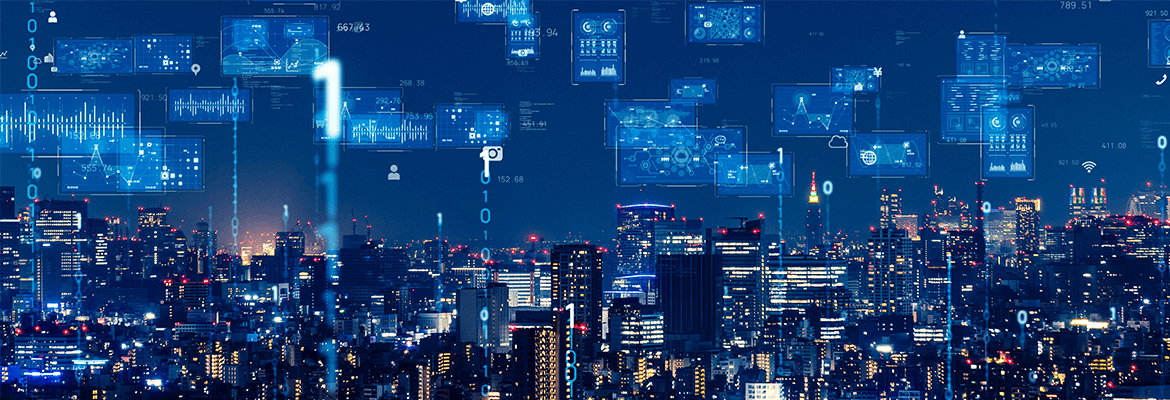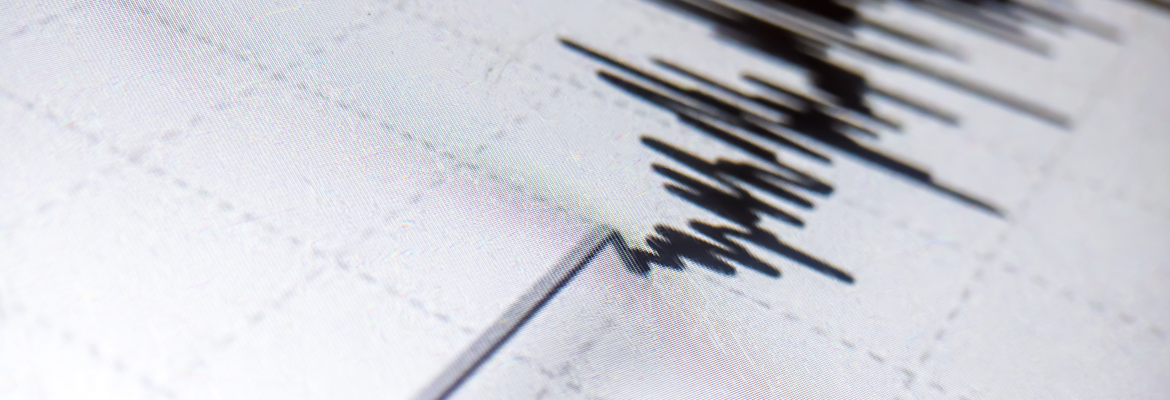日本政府は東日本大震災の教訓を経て、2014年6月に「国土強靭化基本計画」を閣議決定し、巨大災害発生時にも社会インフラの機能を維持する取り組みを始めています。近年、大規模な自然災害が次々と発生するなかで、南海トラフ・首都圏直下型地震やその他不測の事態に備えるため、国土強靭化対策は一層加速が求められています。今回は、その概要と今後必要となる対策などについて解説します。
国土強靭化基本計画策定の背景と目的
 2011年3月に発生した東日本大震災は、日本社会に甚大な被害と私たちに多くの教訓をもたらしました。特に、広範囲にわたるライフラインの停止、物流の混乱、行政機能の麻痺などによって、国家や地域社会の脆弱性が浮き彫りになり、災害に「強い」だけでなく、「しなやかに対応し回復する」社会を構築・維持する必要性が高まります。
2011年3月に発生した東日本大震災は、日本社会に甚大な被害と私たちに多くの教訓をもたらしました。特に、広範囲にわたるライフラインの停止、物流の混乱、行政機能の麻痺などによって、国家や地域社会の脆弱性が浮き彫りになり、災害に「強い」だけでなく、「しなやかに対応し回復する」社会を構築・維持する必要性が高まります。
このような問題意識のもと、2013年12月に「国土強靭化基本法」が成立し、続く2014年6月にその基本方針となる「国土強靭化基本計画」が閣議決定されました。同計画は、平時からの備えを通じて、国の持続的な経済成長に貢献することをめざしており、「人命の保護」「国家・社会の重要な機能の維持」「国民の財産と公共施設に係る被害の最小化」「迅速な復旧・復興」という4つの基本目標を掲げています。
計画の実施にあたっては、さまざまなリスクから人命や社会機能を守るために対策を講じる必要がある15の分野を設定し、施策分野ごとの方針を定めています。例えば、私たちに身近なところの住宅・都市分野では、密集市街地の火災対策や家屋・学校・建物などの耐震化・長期振動対策、エネルギー分野では、供給設備の災害対応力や地域間の総合流通能力の強化、情報通信分野では、長期電力供給停止などに対応する早期復旧体制の整備、交通・物流分野では、耐災害性の向上などが挙げられます。一方、日本全体に関わる国土保全分野では、防災施設の整備などのハード対策と警戒避難体制の整備などのソフト対策を組み合わせた総合的な対策、また老朽化対策分野では、長寿命化計画に基づくメンテナンスサイクルの構築などの方針が策定されています。
なお同計画では、都道府県や市町村ごとの地域特性に応じた「地域強靭化計画」の策定も促進しており、中央集権的な対策から、地域主導による分散型の強靱化への転換も図られています。さらに、「不断の見直し」をすることとし、概ね5年ごとの見直しに加え、必要に応じた変更を行うとしている点も特徴です。
相次ぐ災害と国土強靭化基本法の改訂

国土強靭化基本計画が着実に進められるなか、2016年4月に発生した熊本地震は、広範囲にわたる激しい揺れと断続的な余震活動により、住宅だけでなく社会インフラへも深刻な被害を及ぼしました。多くの避難者が長期間の避難生活を強いられ、避難所運営や住宅再建の課題が顕在化します。2018年7月に発生した西日本豪雨は、記録的な降雨により、広い範囲で浸水、土砂災害、交通網の寸断が発生し、住民の避難行動や行政対応の課題が表面化します。また同年9月に発生した北海道胆振東部地震では、地盤の液状化や大規模な土砂災害に加え、前例のない全域停電(ブラックアウト)が発生し、電力インフラの脆弱性が明らかになりました。
こうした一連の自然災害によって顕在化した課題の解消へ向けて、2018年12月に国土強靭化基本計画は改訂されます。その具体的な内容は、被災者などの健康・避難生活環境の確保、気候変動の影響を踏まえた治水対策、エネルギーや情報通信の多様化・リスク分散化といった、災害から得た知見を反映したもののほか、新技術の活用や国土強靭化に資するイノベーションの推進、地域における防災教育の充実など、社会情勢の変化を踏まえたものを追加しています。また、15の施策分野を見直し、劣悪な避難生活環境、被災者の健康状態の悪化、上水道の長期間供給停止などへの対策を強化する施策を盛り込み、特に緊急を要する施策については、達成目標や実施内容、事業費などを明確にした3か年緊急対策と位置付けています。
さらに2023年7月の改訂では、2014年6月に掲げた4つの基本目標に変更はないものの、これまで進めてきた「国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理」「経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靭化」「災害時における事業継続性確保をはじめとした官民連携強化」の取り組みに加え、「デジタルなど新技術活用による国土強靭化施策の高度化」「地域における防災力の一層の強化(地域力の発揮)」の2点を新たな施策の柱とし盛り込み、国土強靱化にデジタルと地域力を最大限活かしていくものとしています。特にデジタル技術の活用では、デジタルツイン・防災デジタルプラットフォームの構築、次期総合防災情報システムと各省庁などの防災情報関係システムとの自動連携といった防災DXの構築、マイナンバーカードを活用した避難所運営、現場でのロボット・ドローン・AIなどの活用、ICT施工、遠隔監視を施策の推進方針に含めています。
国土強靭化のために今求められている対応
 自然災害以外では、2025年1月に埼玉県八潮市において、大規模な道路陥没事故が発生しました。この事故は、地下に埋設された下水道管路の老朽化が原因とされるもので、これにより道路が遮断されただけでなく、一部地域で水道・下水道の利用制限が発生しました。現在も復旧対応が続くなか、地域住民の生活に大きな混乱をもたらし、その影響が長期化していることから、今回の出来事は都市インフラの安全性に対する関心を一層高めるきっかけとなっています。
自然災害以外では、2025年1月に埼玉県八潮市において、大規模な道路陥没事故が発生しました。この事故は、地下に埋設された下水道管路の老朽化が原因とされるもので、これにより道路が遮断されただけでなく、一部地域で水道・下水道の利用制限が発生しました。現在も復旧対応が続くなか、地域住民の生活に大きな混乱をもたらし、その影響が長期化していることから、今回の出来事は都市インフラの安全性に対する関心を一層高めるきっかけとなっています。
国土交通省などの公表資料によると、日本の下水道処理人口普及率は8割に達しているものの、全国の下水道管路のうち、約7%が一般的な耐用年数と言われる50年を経過しているという実態が報告されています。特に、高度経済成長期に集中的に下水道整備が進められた大都市部においては、老朽化の進行が顕著である一方、これらの老朽化した管路に対する更新・修繕の実施率はわずか1%以下に留まっているという憂慮すべき実態にあります。
また、南海トラフ地震の向こう30年以内の発生確率が引き上げられているほか、首都圏直下型地震の発生も現実的かつ脅威として、南海トラフ地震と並ぶ国内最大級の災害リスクの一つと認識されています。これら背景を踏まえ、「国土強靭化年次計画2025」では計画を推進するため、累計約14.3兆円の予算を投じるほか、2026年度からの5年間の事業費を20兆円強とする方針が示されています。
高度経済成長期に発達した高速道路網なども、政府計画や各高速道路事業者の設備保守計画により橋梁やトンネル補強をはじめとして順次老朽化対策が進められています。道路や建物などのインフラは、建設されたのち年月の経過とともに徐々に老朽化します。私たちはそれらを日々便利に活用していますが、自然災害や老朽化による破損で使用できなくなると、経済活動の停滞や生活が一気に不便になるなど大きな影響が生じます。
このような事態に対応するため、政府・各省庁だけでなく、全国の各自治体においても、防災対策の強化が本格化しています。そして、日本を支える企業では既存のデジタル技術の活用に加え、より耐久性の高い新たな素材や、効率的な点検・補修技術など、国土強靭化に向けた技術開発に取り組んでいます。私たち一人ひとりも、災害時に自分と家族、そして地域を守るために、これまで以上に日々の生活のなかで防災意識を高めていくことが求められていくでしょう。
関連する記事
メールマガジンで配信いたします。